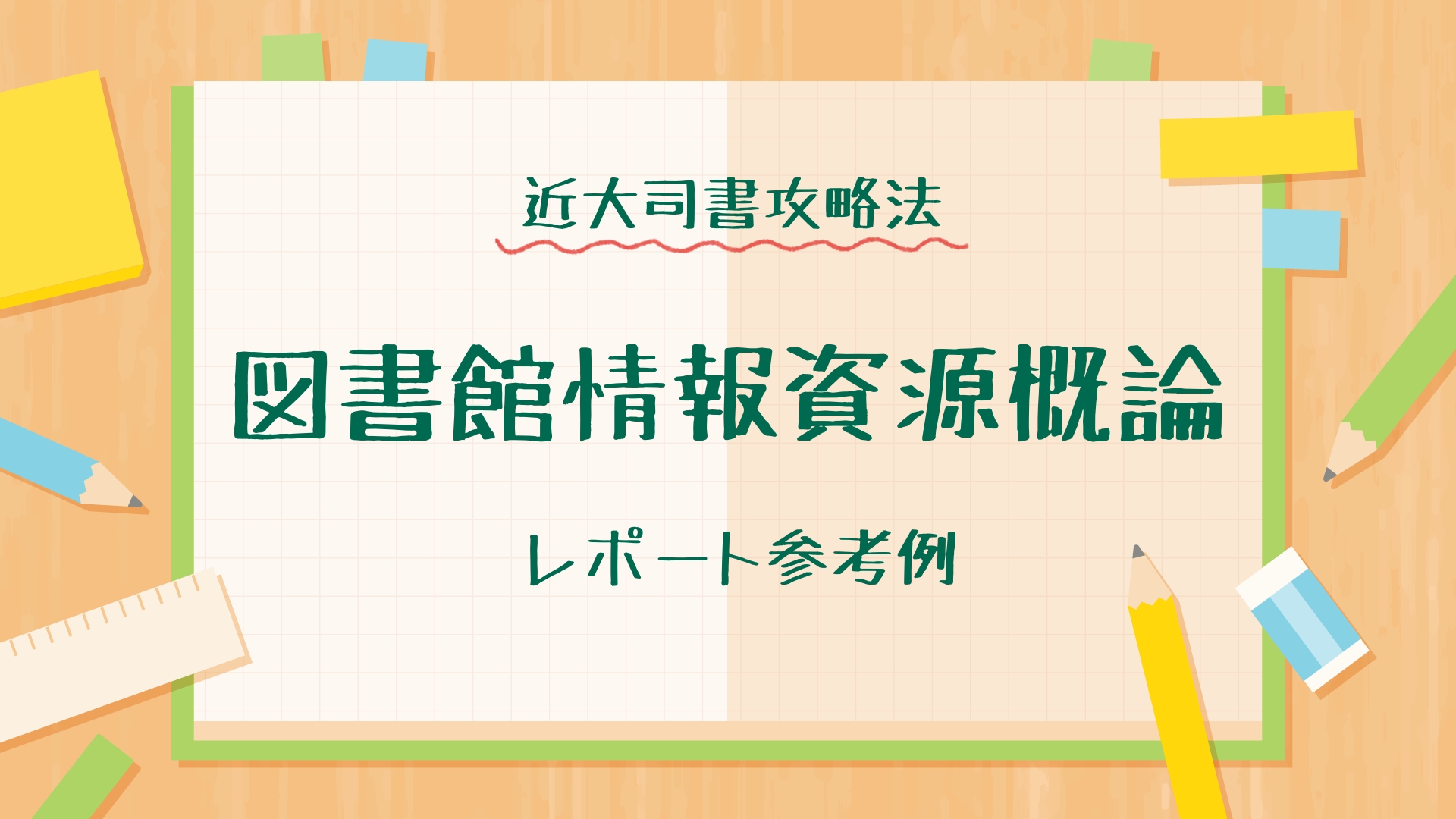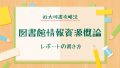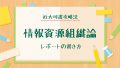このページでは、2023〜2024年度版「図書館情報資源概論」レポートの合格例を掲載しています。
丸写しすると再提出になるため、自分の言葉に置き換えるなど適宜アレンジしてください。
書き方のコツは、こちらのページで説明しています。
レポート全体の注意点や順番については、こちらのページを参考にしてください。
レポート設題
公共図書館が収集するネットワーク情報資源の種類や特徴、提供事例について述べてください。
また、若い世代に対して情報資源の利用をどのように広報・PRしていくべきかあなた自身の考えを含め、論じてください。
解答例
序論
本論では、デジタルアーカイブ、電子図書館の2つのネットワーク情報資源について、その特徴と提供事例、若い世代に効果的な広報・PR方法について論じる。
本論
デジタルアーカイブ
デジタルアーカイブとは、絶版等の理由により入手困難になってしまった資料や古い資料、貴重な資料など、劣化や破損の恐れから一般には貸出、公開されない資料をデジタル化し、インターネット上で公開しているコンテンツのことを指す。
デジタルアーカイブはそれぞれの図書館、研究機関等で作成されているが、それらのメタデータをジャパンサーチなどのアグリゲータがまとめて検索、閲覧できるようにしており、インターネット上の一大データベースとなっている。
実際の提供事例として、東京都立図書館デジタルアーカイブ(TOKYOアーカイブ)などが挙げられる。
TOKYOアーカイブでは、江戸時代から東京府・東京市に続くまでの地図や図面、災害記録のほか、浮世絵や双六などの貴重な資料も提供されている。
また、国立国会図書館には、図書館向けデジタル化資料送信サービスという「国立国会図書館のデジタル化資料のうち、絶版等の理由で入手が困難な資料を全国の公共図書館、大学図書館等の館内で利用できるサービス」が存在する。
これにより、国立国会図書館の承認を受けた図書館が近くにありさえすれば、場所を問わず、全国どこからでも入手困難な資料にアクセスできるようになった。
このように、各図書館が保有する貴重な資料をデジタル化し、誰でもいつでもどこでも等しくサービスを受けることを可能にしたのがデジタルアーカイブである。
昨今では、図書館だけでなく、美術館や博物館などでもデジタルアーカイブが提供されている。
デジタルアーカイブの大きな強みは、インターネットを利用可能な情報端末さえあれば、どこにいようといつでも資料にアクセスすることができるという点である。
若い世代はデジタルネイティブであるため、インターネット上のコンテンツを契機として図書館への立ち寄りを期待したい。
そのためのPR方法としては、同じくインターネットを活用することが最適であると考える。
例えば、面白い資料のデジタルアーカイブや図書館のバーチャルツアーなどの取組をSNSやYouTubeなどを利用して配信することや、インフルエンサーやYouTuberとコラボレーションすることなどが挙げられる。
こうしたインターネットを活用した広報活動をすることで、若い世代にも興味を持ってもらうことに繋がると考える。
電子図書館
電子図書館とは、パソコンやタブレット、スマートフォンなどの情報端末で、電子書籍を借りて読むことができるサービスである。
先述のデジタルアーカイブと大きく異なるのは、電子図書館では今まさに流通している書籍を通常の図書館と同じように借りられるという点である。
電子図書館は、貸出票があればどこでも電子書籍を借りられ、返却できることから、利便性の向上に役立っていると考えられる。
また、電子書籍を貸し出すことから、本の紛失や破損、盗難という心配がないのがメリットである。
さらに、昨今では公共図書館の蔵書数が増えすぎたあまり、所蔵スペースがないという問題も生じているが、電子図書館はこの物理的な制約も受けないに等しい。
個人においても、紙の本は嵩張り、場所を取ることから、若い世代を中心に紙の書籍から電子書籍へと切り替える人が増えている。
実際、電子書籍のレンタルサービスは市場に数多く存在し、若い世代の利用者も多い。
しかしながら、このような商業的サービスは有料、あるいはサブスクリプション形式を取っているケースが多いのが難点である。
それに対して、電子図書館は貸出票さえあれば無料で借りられるため、この最大のメリットを売り込んでいくことが最も効果的であると考える。
電子図書館はまだまだ認知度が低いため、先に挙げたようなSNSの活用や、インターネット上の広告などを用いた宣伝活動によって、まずはその存在を知ってもらうことが新たな利用の促進に繋がるのではないかと考える。
結論
本論では、ネットワーク情報資源の例として、デジタルアーカイブと電子図書館の2つについて、その特徴や若い世代向けのPR方法について論じてきた。
いずれの事例にも共通するのは、デジタルネイティブである若い世代にとって最も身近なデバイスを活用することが、広報にも利用にも有効であるということである。
これから社会が更なるデジタル化を遂げていく中で、公共図書館がその波に遅れず、より発展していくことを期待したい。
参考文献
- 東京都立図書館デジタルアーカイブホームページ[https://archive.library.metro.tokyo.lg.jp/da/top](アクセス日時:2024年8月31日)
- 国立国会図書館ホームページ[https://www.ndl.go.jp/jp/library/service_digi/index.html](アクセス日時:2024年8月31日)
書き方のコツ
書き方のコツは以下のページを参考にしてください。
また、他の科目については以下のページにそれぞれ掲載しています。
- 「生涯学習概論」レポートの書き方
- 「生涯学習概論」レポートの参考例
- 「図書館概論」レポートの書き方
- 「図書館概論」レポートの参考例
- 「図書館情報技術論」レポートの書き方
- 「図書館情報技術論」レポートの参考例
- 「図書館制度・経営論」レポートの書き方
- 「図書館制度・経営論」レポートの参考例
- 「図書館サービス概論」レポートの書き方
- 「図書館サービス概論」レポートの参考例
- 「情報サービス論」レポートの書き方
- 「情報サービス論」レポートの参考例
- 「児童サービス論」レポートの書き方
- 「児童サービス論」レポートの参考例
- 「情報資源組織論」レポートの書き方
- 「情報資源組織論」レポートの参考例
- 「図書・図書館史」レポートの書き方
- 「図書・図書館史」レポートの参考例
- 「図書館サービス特論」レポートの書き方
- 「図書館サービス特論」レポートの参考例
科目終末試験の対策
レポートを提出したら、いよいよ科目終末試験を受験することができます。
科目終末試験の設題や解答例は以下のページに載せているので、試験対策に役立ててください。