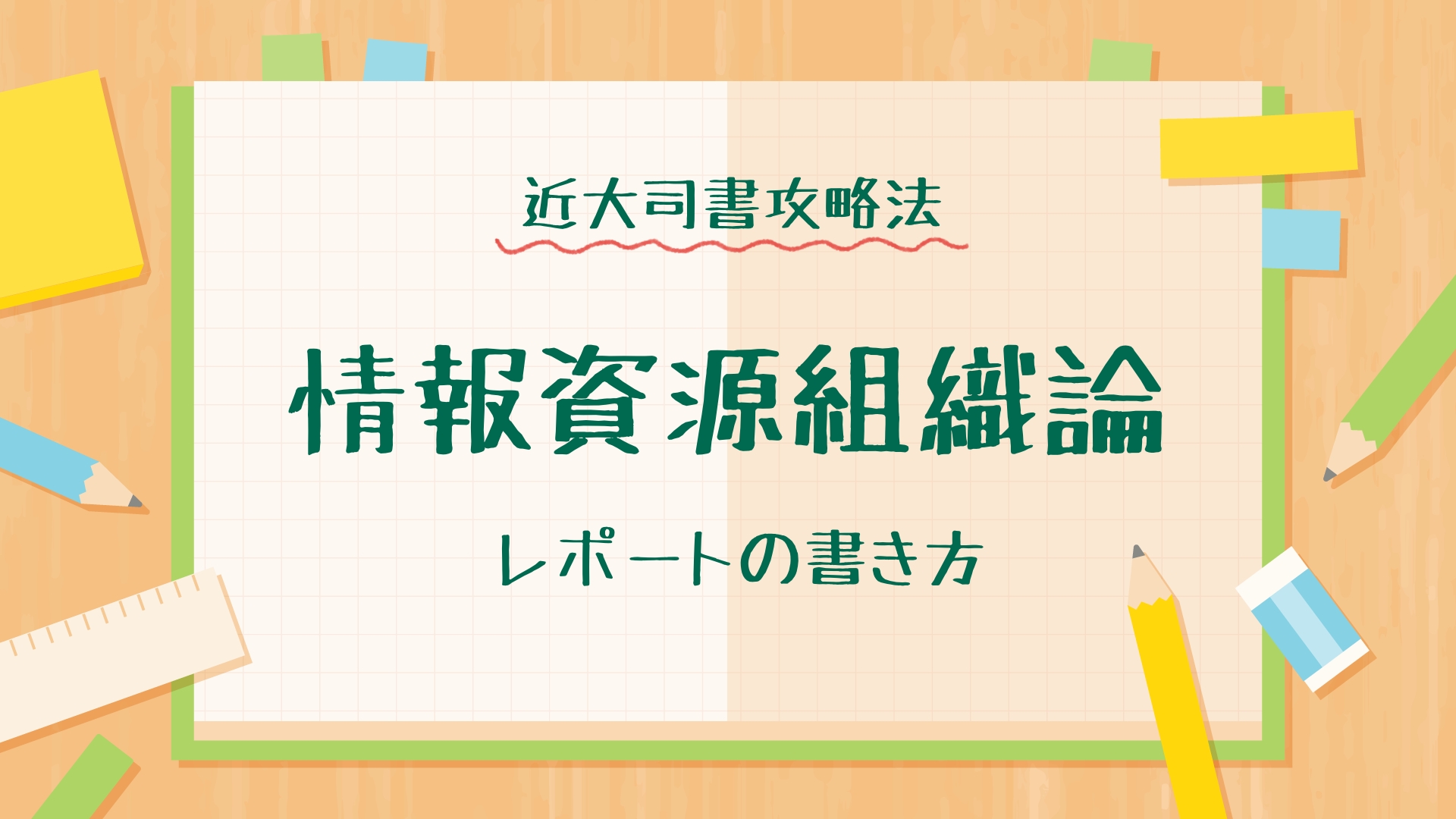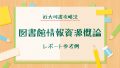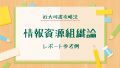このページでは、2023〜2024年度版「情報資源組織論」レポートの書き方を説明しています。
ここで紹介しているやり方は必ずしも正しいとは限らず、あくまでも考え方の一つに過ぎません。
合格レポート例は、こちらのページを参考にしてください。
レポート全体の注意点や順番については、こちらのページで説明しています。
レポート設題
指定したキーワードをすべて使って、各設問の解答を完成させてください。
1.現在、多くの公共図書館や大学図書館で、外部の書誌データを利用した目録作成業務が行われています。集中目録作業と分担目録作業(=共同目録作業)、それぞれの特徴(意味や役割、課題など)を明確にし、さらに今後の目録作成業務のあり方について自らの見解をまとめてください。(1,000字)
<キーワード:MARC、集中目録作業、分担目録作業、総合目録、書誌ユーティリティ>
2.地域の図書館(公共図書館)での現地調査もしくは調査対象館のHPの蔵書検索により、「蔵書の所在記号(背ラベル)の付与のしかた」について複数ケースを洗い出し、気づいたことをまとめてください。さらに、調査で得た内容や関連情報をもとに、書架分類と書誌分類という二つの点から、NDCの分類(記号)を活用することの意義や課題について考察してください。尚、調査対象館は“NDCを採用する近隣の公共図書館”で、取り扱う情報資源は“紙資料”とします。(1,000字)
<キーワード:書架分類、書誌分類、目録、配架(テキストでは排架を使用)、所在記号>
評価のポイント
このレポートの評価基準は、指定されたキーワードを全て正しい意味で使っているかです。
語句の意味をきちんと理解していなければいけませんが、テキストだとさっぱり意味が分からない、難しい、という人も多いようなので、とりあえず他の人のレポートを見るなりググるなりしましょう。
設問1と設問2はそれぞれ文字数が決まっているので、その点も気をつけてください。
書き方のコツ
解答欄を確認する!
設題が2つある科目の場合、解答欄が設題ごとに設けられているパターンと、解答をまとめて1つの解答欄に記述するパターンがあります。
「情報資源組織論」は前者の解答欄2つパターン(1つの設題に対し1000字制限)なので、解答欄の文字数に合わせて序論本論結論の構成を変える必要があります。
テキストの該当箇所を抜き出す!
設題1の「集中目録作業と分担目録作業」は、テキストに書いてあることをそのまま抜き出せばいいです。
どこを抜き出したらいいか分からないという人は、先輩たちの合格レポートを見てみましょう。
テキストはみんな同じものを使用しているはずなので、誰が書いても似たような回答になります。
そのため、複数人のレポートに共通している内容が模範解答であるということです。
該当箇所が見つかったら、説明を自分の言葉に置き換えつつ、それっぽく書いていきます。
なお、レポート添削には剽窃検知ソフトが入っているので、他人のレポートを丸写しすると即バレて再提出になります。
設題は2年ごとに切り替わるため、参考になるのは直近の回答例ですが、設題が同じでなくても使用しているテキストの内容は概ね一緒なので、過去のレポート例も覗いてみましょう。
実際に図書館の本を調べよう!
設題2は、実際に図書館の本を何冊か調べてみて、分類記号にどういう特徴があるのかを調べるものです。
現地調査はもちろんですが、蔵書検索も必ず行ってください。
そうすると、後述する「書架分類」と「書誌分類」の意義や課題が考えやすくなります。
同じテーマの本を複数取り上げる!
まず、NDC(日本十進分類法)がどういうものなのかをはっきりさせておきましょう。
NDCは、テーマによって本を10のカテゴリーに分け、それぞれのカテゴリーの番号(0~9)を付与して本を管理しやすくするものです(詳しくはググってください)。
今回のレポートでは、NDCを利用することの意義と課題を考える必要があるので、この特徴を逆手に取って、同じテーマの本を何冊か調べてみます。
NDCは本のテーマで本を分類するものなので、テーマが同じなら、記号も同じになるはずですよね?
ですが、実際に図書館で本を探そうとすると、似たような内容なのに、なぜか違う棚に置いてある本がいくつもあります。
例えば、蔵書検索で「スマホ依存」をキーワードに検索してみると、「総記」から「医学」まで様々な所在記号の本が出てきます。
このやり方で、同じテーマなのに所在記号が違う本をいくつかピックアップしてみてください。
「書架分類」と「書誌分類」の違いを考える!
「書架分類」と「書誌分類」は、ざっくり説明すると以下のような感じです。
書架分類:本をどのカテゴリーの棚に置くか?
書誌分類:本をどのカテゴリーに分類するか?
そのため、順番としては「書誌分類」で所在記号を決める→「書架分類」でどの棚に置くか決めるという流れになります。
たまに2つの所在記号を持つ本がありますが、あれは「書誌分類で2つのカテゴリーに分けられたけど、本自体は1冊しかないから、書架分類では1つのカテゴリーの棚にしか置けなかった」ということです。
先ほどの「スマホ依存」を例に考えてみましょう。
スマホ依存が健康に及ぼす害について知りたい人は、恐らく「医学」の棚を探すと思います。
一方で、どうして人はスマホ依存になってしまうのかを知りたい人は、「心理学」の棚を探すかもしれません。
たとえ、答えを見つけられる本が他のカテゴリーの棚に置いてあったとしてもです。
「書架分類」の観点から見たNDCのデメリットはここにあります。
ですが、蔵書検索をすることで、配架場所の垣根を越えて本を探すことができるようになります。
蔵書検索で使用する目録は、「書誌分類」によって作られているものです。
そのため、「書誌分類」の観点から見ると、様々なテーマを併せ持つ本を一挙に検索できるという点で、NDCにはメリットがある訳です。
レポートの参考例
実際のレポートは以下のページを参考にしてください。
また、他の科目については以下のページにそれぞれ掲載しています。
- 「生涯学習概論」レポートの書き方
- 「生涯学習概論」レポートの参考例
- 「図書館概論」レポートの書き方
- 「図書館概論」レポートの参考例
- 「図書館情報技術論」レポートの書き方
- 「図書館情報技術論」レポートの参考例
- 「図書館制度・経営論」レポートの書き方
- 「図書館制度・経営論」レポートの参考例
- 「図書館サービス概論」レポートの書き方
- 「図書館サービス概論」レポートの参考例
- 「情報サービス論」レポートの書き方
- 「情報サービス論」レポートの参考例
- 「児童サービス論」レポートの書き方
- 「児童サービス論」レポートの参考例
- 「図書館情報資源概論」レポートの書き方
- 「図書館情報資源概論」レポートの参考例
- 「図書・図書館史」レポートの書き方
- 「図書・図書館史」レポートの参考例
- 「図書館サービス特論」レポートの書き方
- 「図書館サービス特論」レポートの参考例
科目終末試験の対策
レポートを提出したら、いよいよ科目終末試験を受験することができます。
科目終末試験の設題や解答例は以下のページに載せているので、試験対策に役立ててください。
- 科目終末試験の注意点と設題一覧
- 「図書館サービス概論」科目終末試験の解答例
- 「情報サービス論」科目終末試験の解答例
- 「児童サービス論」科目終末試験の解答例
- 「情報資源組織論」科目終末試験の解答例
- 「図書・図書館史」科目終末試験の解答例
- 「図書館情報技術論」科目終末試験の解答例
- 「図書館情報資源概論」科目終末試験の解答例
メディア授業の科目終末試験
「情報資源組織論」のレポートを提出すると、面接授業科目の「情報資源組織演習」を受講できるようになります。
メディア授業を選択した場合の受講方法と科目終末試験の対策については、以下のページで説明しています。