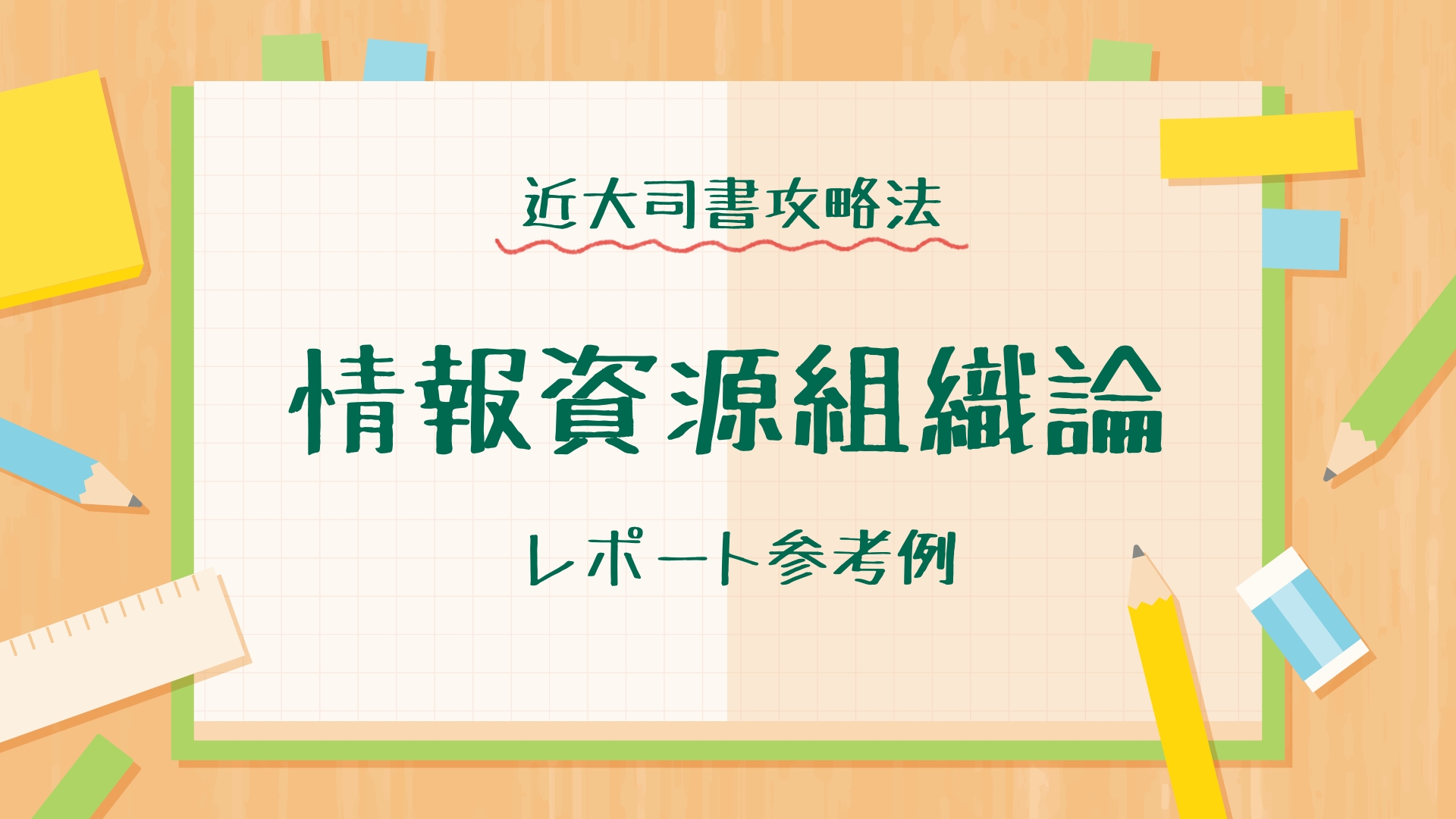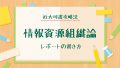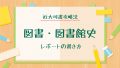このページでは、2023〜2024年度版「情報資源組織論」レポートの合格例を掲載しています。
丸写しすると再提出になるため、自分の言葉に置き換えるなど適宜アレンジしてください。
書き方のコツは、こちらのページで説明しています。
レポート全体の注意点や順番については、こちらのページを参考にしてください。
レポート設題
指定したキーワードをすべて使って、各設問の解答を完成させてください。
1.現在、多くの公共図書館や大学図書館で、外部の書誌データを利用した目録作成業務が行われています。集中目録作業と分担目録作業(=共同目録作業)、それぞれの特徴(意味や役割、課題など)を明確にし、さらに今後の目録作成業務のあり方について自らの見解をまとめてください。(1,000字)
<キーワード:MARC、集中目録作業、分担目録作業、総合目録、書誌ユーティリティ>
2.地域の図書館(公共図書館)での現地調査もしくは調査対象館のHPの蔵書検索により、「蔵書の所在記号(背ラベル)の付与のしかた」について複数ケースを洗い出し、気づいたことをまとめてください。さらに、調査で得た内容や関連情報をもとに、書架分類と書誌分類という二つの点から、NDCの分類(記号)を活用することの意義や課題について考察してください。尚、調査対象館は“NDCを採用する近隣の公共図書館”で、取り扱う情報資源は“紙資料”とします。(1,000字)
<キーワード:書架分類、書誌分類、目録、配架(テキストでは排架を使用)、所在記号>
解答例
序論
本論では、公共図書館や大学図書館で行われている目録作成業務と、NDCによる所在記号の付与方法について論じる。
また、それらの分析を通して、公共図書館が利便性向上のためにどのような取組を行ってきたのか、その意義を考察する。
本論
目録作成業務の種類と特徴、今後のあり方について
公共図書館や大学図書館で行われている目録作成業務は、集中目録作業と分担目録作業(=共同目録作業)の2種類に分けられる。
まず、集中目録作業とは、1つの図書館または組織が集中的に目録を作成する作業のことである。
これにより、1つの図書館が作成した目録を他館でも活用することができるようになった。
他館への頒布においては、当初は印刷カードが用いられていたが、現在はコンピューター処理が可能なMARC(MAchine Readable Cataloging)という目録データベースを用いることが多い。
ただし、実際に本が図書館に納品されるタイミングと、目録の作成及び頒布のタイミングには一定のタイムラグが生じるため、新刊書を受け入れる際に、目録の作成及び頒布が間に合っておらず、実物はあるものの利用者に提供することはできないという課題もある。
次に、分担目録作業とは、複数の図書館または組織が分担して目録を作成する作業のことである。
これにより、複数の図書館の目録が統合され、複数の図書館の所蔵資料全てについて検索が可能な総合目録を構築することができるようになった。
目録作成作業を分担することで、業務の効率化や費用削減が実現できた一方、業務負担の偏りや目録の質のばらつきも課題として挙げられる。
そのため、書誌ユーティリティと呼ばれる総合目録の作成機関が形成され、現在ではそれらの機関から総合目録が提供されることが多い。
以上見てきたように、集中目録作業、分担目録作業はいずれも一長一短あり、これらの長所と短所を補う形でどのように併用していくことが今後の鍵となると考えられる。
具体的には、新刊書の目録作成に特化した書誌ユーティリティの総合目録からMARCに目録データを移行できるなどの工夫である。
また、業務負担の軽減には、人工知能の力を借りることも有効なのではないかと考える。
バーコードを読み取ると、人工知能により自動で書誌情報が目録に登録されるなどの方策が有効だと考えられる。
所在記号の付与方法の調査及びNDCの意義と課題について
NDC(Nippon Decimal Classification)とは、資料をその主題に即した9つの区分によって分類し、それぞれの区分に対応した0から9までの分類記号を組み合わせることによって所在記号を割り振り、管理する図書分類法である。
今回は、◯◯図書館での現地調査をもとに、このNDCによってどのように所在記号が付与されているのか、それによる長所と短所について分析する。
まず、実際にどのように所在記号が付与されるのかを見ていく。
今回は例として、以下の2冊を取り上げた。
- 所在記号◯◯『デジタル・ミニマリスト』
- 所在記号◯◯『スマホ脳』
これらの資料を取り上げた理由は、スマートフォンやデジタルデトックスといった近年出現した新たな概念が、古くから使用されているNDCの分類でどのように扱われているのかを知りたかったからである。
『デジタル・ミニマリスト』、『スマホ脳』の内容は、いずれも幅広い主題に跨っていることが分かる。
NDCは書架分類の点から見れば、誰が見ても明白で分かりやすく、資料が探しやすいという長所がある。
しかし、このような複数の主題を持った資料をNDCによって1つの主題に分類せざるを得ないのは、配架の観点から見ると利便性に問題がある。
一方で、書誌分類の観点から見れば、目録を検索することで、違う棚に配架されている同じ資料も見つけやすくなるという長所がある。
結論
本論では、目録作成業務とNDCの意義及び課題について論じ、公共図書館がどのような工夫をして利便性の向上に努めてきたかを見てきた。
目録作成も分類も、図書館職員の力なくしては成り立たない業務であることが改めて理解できた。
これからはより業務効率を高めるため、人工知能の力を借りるなどして、より迅速で正確な資料の管理を実現することを期待したい。
参考文献
- カル・ニューポート『デジタル・ミニマリスト』早川書房、2019年
- アンデシュ・ハンセン『スマホ脳』新潮新書、2020年
書き方のコツ
書き方のコツは以下のページを参考にしてください。
また、他の科目については以下のページにそれぞれ掲載しています。
- 「生涯学習概論」レポートの書き方
- 「生涯学習概論」レポートの参考例
- 「図書館概論」レポートの書き方
- 「図書館概論」レポートの参考例
- 「図書館情報技術論」レポートの書き方
- 「図書館情報技術論」レポートの参考例
- 「図書館制度・経営論」レポートの書き方
- 「図書館制度・経営論」レポートの参考例
- 「図書館サービス概論」レポートの書き方
- 「図書館サービス概論」レポートの参考例
- 「情報サービス論」レポートの書き方
- 「情報サービス論」レポートの参考例
- 「児童サービス論」レポートの書き方
- 「児童サービス論」レポートの参考例
- 「図書館情報資源概論」レポートの書き方
- 「図書館情報資源概論」レポートの参考例
- 「図書・図書館史」レポートの書き方
- 「図書・図書館史」レポートの参考例
- 「図書館サービス特論」レポートの書き方
- 「図書館サービス特論」レポートの参考例
科目終末試験の対策
レポートを提出したら、いよいよ科目終末試験を受験することができます。
科目終末試験の設題や解答例は以下のページに載せているので、試験対策に役立ててください。
- 科目終末試験の注意点と設題一覧
- 「図書館サービス概論」科目終末試験の解答例
- 「情報サービス論」科目終末試験の解答例
- 「児童サービス論」科目終末試験の解答例
- 「情報資源組織論」科目終末試験の解答例
- 「図書・図書館史」科目終末試験の解答例
- 「図書館情報技術論」科目終末試験の解答例
- 「図書館情報資源概論」科目終末試験の解答例
メディア授業の科目終末試験
「情報資源組織論」のレポートを提出すると、面接授業科目の「情報資源組織演習」を受講できるようになります。
メディア授業を選択した場合の受講方法と科目終末試験の対策については、以下のページで説明しています。