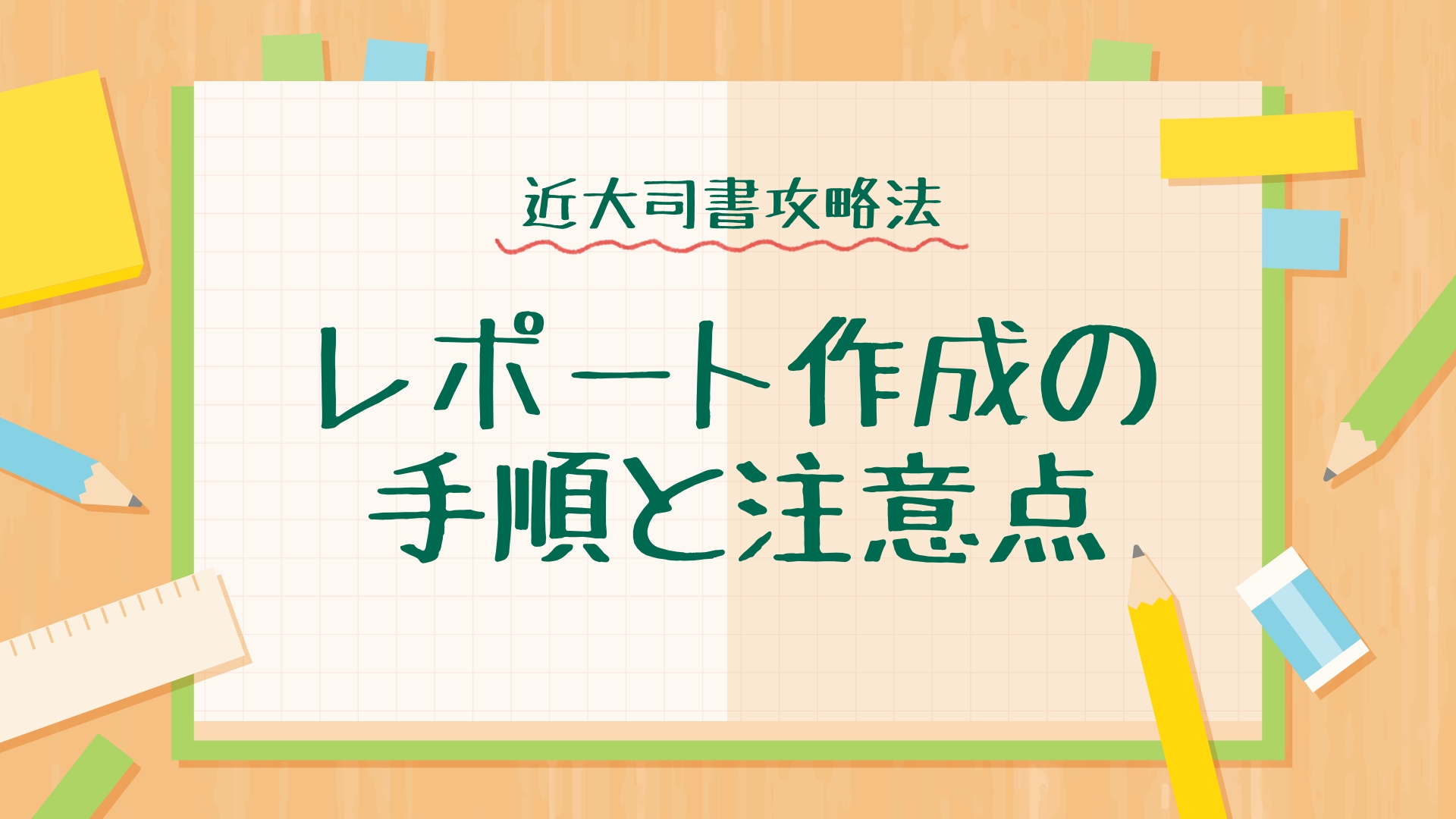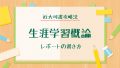近畿大学の司書課程に入学して最初にぶち当たる壁がレポート作成です。
各科目の単位を取得するためには、レポートと科目終末試験の両方の合格が必須ですが、科目終末試験を受けるためには事前にレポートを提出していなければなりません(合否は問わない)。
レポートと言われても何をどう書けばいいのか分からない、何度書いても再提出になってしまう…そんな方も中にはいるのではないでしょうか。
ここでは、そんな悩める近大生の方々に向けて、私なりにレポート作成の手順と注意点について解説します。
科目終末試験については、こちらのページを参考にしてください。
レポート作成の注意点
レポートを書くにあたり、まず最初に知っておきたいことは、以下の2つです。
「情報サービス論」と「情報資源組織論」が最優先!
必修科目のうち、面接授業科目の「情報サービス演習」と「情報資源組織演習」は、事前にレポートを提出していないと受講の申し込みができません。
メディア授業を受ける場合、受講申し込みの締切は前期4月中旬、後期10月中旬とかなり早いため、何よりもまず「情報サービス論」と「情報資源組織論」のレポートを仕上げ、提出する必要があります。
メディア授業の科目終末試験は年に2回(前期7月と後期1月)しかないので、最初の学期で受講できると、万が一試験に落ちてしまっても再びチャンスがあるので安心です。
困ったときは「掲示板」を参考にする!
KULeD(近大のポータルサイト)には、司書課程の学生が書き込める掲示板があります。
掲示板では、レポートの書き方や合格のコツについて、学生同士で相談していることがあります。
そのため、レポートや試験のことで悩んだら、一度掲示板を覗いてみることをオススメします。
掲示板は、KULeDサイドメニューの「掲示板」>「司書の広場」から見ることができます。
レポート作成の手順
ここからは、実際にどのようにしてレポートを作成するかを説明します。
レポートの設題を確認する!
テキストを読み始める前に、まず各科目のレポートの設題を確認します。
設題は、KULeDの「レポート提出」から確認することができます。
また、2025年現在では「梅信」>「書式ダウンロード」にもレポート設題集が掲載されています。
なお、設題は2年ごとに切り替わるため注意してください。
参考までに、2023~2024年度のレポート設題は以下のようなものでした。
※選択科目は「図書・図書館史」と「図書館サービス特論」を掲載しています。
「生涯学習概論」の設題
① 生涯学習支援のために図書館が果たす役割とは何かについて述べなさい。
② 生涯学習を振興するために、社会教育行政や施設の基本的な役割について述べなさい。
「図書館概論」の設題
公共図書館を1つ選び、レポートを作成しなさい。以下について記入すること。
- 図書館の正式名称と所在地
- 立地、予算、蔵書数、蔵書の年間増加数、貸出数、業務別職員数(内、過去数年間の採用者数、司書有資格者数)、収容座席数
- 図書館サービスの種類と内容
- 見学先の図書館に期待すること、改良すべき点、全体の感想等
「図書館情報技術論」の設題
レポート執筆者が考える「図書館を最大限に活用するため」または「図書館の利用を円滑にするため」という観点で着目した情報技術について、それらへの理解を深めた上で自身の意見を論じてください。
「図書館制度・経営論」の設題
「図書館経営の基本思考」における「未来思考」の5点について簡潔明瞭に説明した後、その「未来思考」を受けて、今後の専門職としての司書のあるべき姿を論じるとともに、それに伴う図書館運営のあり方を、貴方自身の考え方を含め論じて下さい。
「図書館サービス概論」の設題
身近な公共図書館(都道府県立より、市町村立が望ましい)を観察し、このテキストに書いてあることと比較しつつ、その図書館の特徴を述べ、またあなたの具体的で実現可能な希望を列挙してください。
「情報サービス論」の設題
大学図書館における利用指導の内容7点を挙げ、それぞれについて簡潔に述べた後、利用教育の手段についてはどうあるべきか、最近の動向にも配慮し、貴方自身の考え方を含め論じてください。
「児童サービス論」の設題
① 児童サービスにおける読書の意義と役割について述べ、また図書館における児童サービスがなぜ重要であるかを述べなさい。
② 児童資料の種類と特性について述べ、児童サービスの実践においてそれらの資料をどのような場でどのように生かすべきかを述べなさい。
「図書館情報資源概論」の設題
公共図書館が収集するネットワーク情報資源の種類や特徴、提供事例について述べてください。
また、若い世代に対して情報資源の利用をどのように広報・PRしていくべきかあなた自身の考えを含め、論じてください。
「情報資源組織論」の設題
指定したキーワードをすべて使って、各設問の解答を完成させてください。
1.現在、多くの公共図書館や大学図書館で、外部の書誌データを利用した目録作成業務が行われています。集中目録作業と分担目録作業(=共同目録作業)、それぞれの特徴(意味や役割、課題など)を明確にし、さらに今後の目録作成業務のあり方について自らの見解をまとめてください。(1,000字)
<キーワード:MARC、集中目録作業、分担目録作業、総合目録、書誌ユーティリティ>
2.地域の図書館(公共図書館)での現地調査もしくは調査対象館のHPの蔵書検索により、「蔵書の所在記号(背ラベル)の付与のしかた」について複数ケースを洗い出し、気づいたことをまとめてください。さらに、調査で得た内容や関連情報をもとに、書架分類と書誌分類という二つの点から、NDCの分類(記号)を活用することの意義や課題について考察してください。尚、調査対象館は“NDCを採用する近隣の公共図書館”で、取り扱う情報資源は“紙資料”とします。(1,000字)
<キーワード:書架分類、書誌分類、目録、配架(テキストでは排架を使用)、所在記号>
「図書・図書館史」の設題
日本または西洋のどちらかを選び、それぞれの時代(古代、中世、近世、近代以降)の図書館発展の特徴をコンパクトに要約し、かつ私見(400字程度のまとめ)を述べてください。
「図書館サービス特論」の設題
身近にある公共図書館を実際に観察し、その図書館で行われている課題解決支援サービスの内容及び特徴を述べると共に、設置されている地域の課題を考えると他にどのようなサービスが実現可能か具体的に提示しなさい。
レポートを書く順番を決める!
こうして設題を見ると、レポートには「テキストで得た知識をまとめ、自分の考えを述べるもの」と「テキストで得た知識を踏まえ、実際に特定の図書館を調査して結果をまとめるもの」の2パターンあることが分かります。
ざっくり振り分けると以下のような感じです。
テキストの内容をまとめるパターン
- 生涯学習概論
- 図書館情報技術論
- 図書館制度・経営論
- 情報サービス論
- 児童サービス論
- 図書館情報資源概論
- 情報資源組織論(設題1)
- 図書・図書館史
調査結果をまとめるパターン
- 図書館概論
- 図書館サービス概論
- 図書館サービス特論
- 情報資源組織論(設題2)
レポートを作成するにあたって、どの科目から手をつけるかは完全に自由です。
ですが、科目終末試験を効率よく受けるためには、最初に「調査結果をまとめる」レポート群から片づけることをオススメします。
公式の学習方法は「テキストを一通り読んでからレポートに取り組む」ですが、何を書くべきなのか頭に入れてからテキストを読んだ方が後々レポートも書きやすいと思うからです。
参考までに、実際に私が提出した順番を紹介します。
返却までの日数も書いたので、学習計画を立てるときの目安にしてください。
なお、私は選択科目で「図書・図書館史」と「図書館サービス特論」を選びました。
| 科目(提出順) | 返却までの日数 |
| ① 図書館概論 | 22日 |
| ② 図書館サービス概論 | 5日(再提出時:7日) |
| ③ 図書館サービス特論 | 22日(再提出時:22日) |
| ④ 図書館情報技術論 | 44日 |
| ⑤ 図書館情報資源概論 | 39日 |
| ⑥ 情報サービス論 | 11日 |
| ⑦ 情報資源組織論 | 7日 |
| ⑧ 図書・図書館史 | 30日 |
| ⑨ 図書館制度・経営論 | 22日 |
| ⑩ 児童サービス論 | 13日 |
| ⑪ 生涯学習概論 | 13日 |
私はとにかく最短で攻略したかったため、テキストの読め込みが必要な科目は後回しにして、調査結果をまとめる系の科目から取り組みました。
以下では、具体的な順番の考え方について説明します。
1.「図書館を調査する」レポートを片づける!
- 図書館概論
- 図書館サービス概論
- 図書館サービス特論
上記のレポートは正直テキストを読まなくても書けそうだったので、まずはこの3科目を片づけていきます。
特に「図書館サービス概論」、「図書館サービス特論」の内容は使い回せそうだったので、この2つは同時に書き進めました。
2.返却が遅いレポートを片づける!
- 図書館情報技術論
- 図書館情報資源概論
この2科目は返却が遅いことで有名らしいです(掲示板には60日以上かかったという人も!)。
しかも返却は遅いくせに再提出になりやすい科目なので、早々に片づけてしまいます。
これらのレポートも内容が使い回せそうだったので、同時に書き進めました。
3.面接授業科目のレポートを片づける!
- 情報サービス論
- 情報資源組織論
私は入学が遅かったため、残念ながら前半のメディア授業は申し込みできませんでした。
後半のメディア授業申込が迫ってきたので、上記のレポートに取りかかります。
レポート作成時の注意点でも触れましたが、早めに入学した場合は何よりもまずこの2科目から片づけてください。
4.「テキストをまとめる」レポートを片づける!
- 図書・図書館史
- 図書館制度・経営論
- 児童サービス論
- 生涯学習概論
上記の科目はテキストの読み込みが必要なので、自分にとって取っつきやすい科目から取り組んでいきましょう。
私はテキストをザッと見た結果、とりあえず比較的読みやすそうだった「図書・図書館史」から始めてみました。
「図書館制度・経営論」、「児童サービス論」、「生涯学習概論」も、ネット上に転がっている他の人の合格レポートを参考にしながら、ひとまず形にしてみます。
この3つは正直どこが評価基準なのかよく分かりませんでしたが、返却時の講評で採点ポイントを教えてもらえるはずなので、とりあえず一度それっぽいことを書いて出してみて、再提出のときにまた直せばいいや!と気楽に臨みました。
また、先人達の合格レポートをいくつか読んでみると、共通して書かれている内容が発見できるため、ある程度採点ポイントを予測することができます。
テキストをまとめる系のレポートだと、他人のレポートと内容が似通ってしまうのは必然なので、丸写しにならないよう自分の言葉に置き換えつつ、いろんな人のレポートからちょっとずつ拝借していくのも一つの手です。
自分の学習ペースに合った順番を見つけよう!
私は楽・効率重視だったのでこのような順番になりましたが、人によってやり方は様々です。
とにかく最短取得を目指す人
→「図書館情報技術論」などレポートの返却が遅い順に提出する!
テキストを読むのが苦手、難しい内容だと挫折してしまう人
→「図書・図書館史」など比較的テキストが薄い・易しい科目から取りかかる!
しっかり基本を押さえた上で理解を深めていきたい人
→「図書館概論」など初歩的なテキストから読んでみる!
KULeDの掲示板でも、レポートの順番に関するアドバイスはちらほら見かけたので、併せて参考にしてみてください。
レポートの採点ポイントを知る!
近大司書のレポートは、合格か不合格(再提出)かで判断されます。
5段階評価ではないので、ここが科目終末試験とは違うところです。
どんなにいいレポートを書いたとしても、採点ポイントを押さえていなければ合格はできません。
そのため、まずは各科目のレポートの評価基準と、書き方のコツを調べましょう。
私なりに分析した評価基準と書き方のコツ、実際に合格したレポートの参考例を以下にまとめたので、よかったら参考にしてみてください。
「生涯学習概論」の書き方と参考例
「図書館概論」の書き方と参考例
「図書館情報技術論」の書き方と参考例
「図書館制度・経営論」の書き方と参考例
「図書館サービス概論」の書き方と参考例
「情報サービス論」の書き方と参考例
「児童サービス論」の書き方と参考例
「図書館情報資源概論」の書き方と参考例
「情報資源組織論」の書き方と参考例
「図書・図書館史」の書き方と参考例
「図書館サービス特論」の書き方と参考例
レポートを書いてみる!
ここまできたら、あとは実際にレポートを書くだけです。
まずは自分で書いてみて、行き詰まったら先人達のレポートやアドバイスも参考にしながら、どんどん書き進めていきましょう。
レポートを書く際のテクニックは2つです。
Wordやメモ帳で下書きする!
レポートの提出はKULeDから行います。
Wordなどのファイル形式で提出するのではなく、KULeDのレポート作成フォームに直接文字を入力して提出する仕様です。
ですが、KULeDのレポート作成フォームではコピー&ペーストができません。
そのため、もし再提出になってしまうと、また一から手入力し直すことになってしまいます。
二度手間を防ぐためにも、まずはWordやメモ帳などで下書きすることをオススメします。
「ユーザー辞書」を使ってKULeDに入力する!
完成したレポートは、パソコンやスマートフォンの「ユーザー辞書」機能を使って作成フォームに写していきましょう。
「ユーザー辞書」とは、ある特定の単語や定型文に任意の読み方を指定して、一発変換できるようにする機能です。
レポートの内容を一度ユーザー辞書に登録して、KULeDのフォーム上で文字を変換すれば、間接的にコピペをすることができます。
WindowsでもIMEの単語登録を利用できますが、オススメはiPhoneやMacの「ユーザ辞書」です。
Windowsでは一度に登録できる単語の文字数が60字程度ですが、iPhoneやMacではそれよりも遥かに多い文字数を登録することができます。
iPhoneの場合は、「設定」>「一般」>「キーボード」>「ユーザ辞書」から単語登録できます。
文字数制限があるため、2〜3回に分けて登録する必要がありますが、フォームに一から手入力するよりも断然効率が上がるので、ぜひ試してみてください。
一発合格を目指して頑張ろう!
以上がレポート作成の手順と注意点になります。
私の学びが少しでも皆さんのお役に立てば嬉しいです。
ここまでお読みくださりありがとうございました!