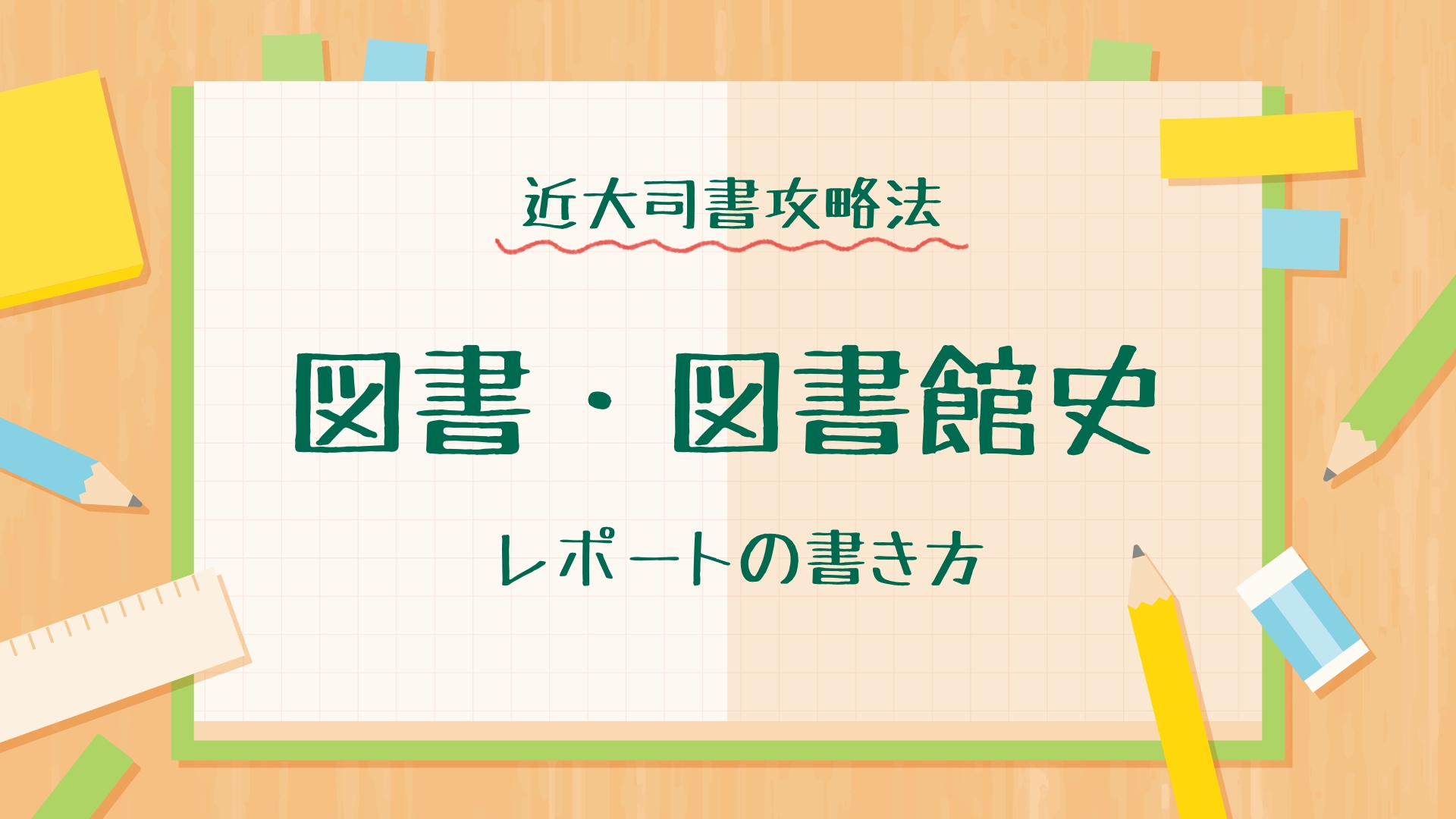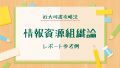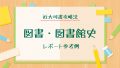このページでは、2023〜2024年度版「図書・図書館史」レポートの書き方を説明しています。
ここで紹介しているやり方は必ずしも正しいとは限らず、あくまでも考え方の一つに過ぎません。
合格レポート例は、こちらのページを参考にしてください。
レポート全体の注意点や順番については、こちらのページで説明しています。
レポート設題
日本または西洋のどちらかを選び、それぞれの時代(古代、中世、近世、近代以降)の図書館発展の特徴をコンパクトに要約し、かつ私見(400字程度のまとめ)を述べてください。
評価のポイント
このレポートの評価基準は、各時代の情報伝達媒体、生産技術・生産量、図書館利用者の変化、図書館の役割の変化について書かれているかです。
テキストの内容をまとめ、そこから導き出される考察を書くだけなので、比較的易しいレポートと言えます。
最後の「私見」は、ただ自分の感想を述べるのではなく、テキストの内容を踏まえた考察を書くことが求められているので、そこだけ注意しましょう。
書き方のコツ
テキストの内容を要約する!
日本と西洋どちらについて書くかを決めたら、早速テキストの該当箇所を抜き出していきます。
古代、中世、近世、近代以降の4時代に分けて書くので、各時代400字程度でまとめるとバランスがよくなります。
その際、必ず取り上げなければならないのは、以下の要素です。
- その時代の図書館を象徴するキーワード(図書館の種類や名前)
- その時代の情報伝達媒体は何か
- その時代の情報伝達媒体の生産技術・生産量
- 図書館利用者の変化
400字に収めようとすると、これだけでもかなり文字数を食われてしまいます。
そのため、各時代の図書館の役割は「私見」で記述すると、考察にもなるし文字数にもゆとりが出るしで一石二鳥です。
ここはあくまで要約なので、テキストに書かれている事実のみを淡々と記述して、自分の見解や考察は後回しにしましょう。
各時代の図書館の役割を考える!
私は西洋で書きましたが、各時代の図書館の役割がどうだったのか、テキストにははっきりと明記されていません(特に近代以降)。
そのため、この点については、図書館利用者の変化などの情報をもとに、自分で考える必要があります。
図書館という施設が開設者や利用者にとってどういう意味を持ち、どんな役割を担ってきたのかは、開設者の社会的役割や利用者の層、所蔵していた書物の種類から窺い知ることができます。
行き詰まったら他の人のレポートの合格例なども参考にしながら、各時代の図書館の役割がどのように変化していったのか、自分の考えを書いていきましょう。
レポートの参考例
実際のレポートは以下のページを参考にしてください。
また、他の科目については以下のページにそれぞれ掲載しています。
- 「生涯学習概論」レポートの書き方
- 「生涯学習概論」レポートの参考例
- 「図書館概論」レポートの書き方
- 「図書館概論」レポートの参考例
- 「図書館情報技術論」レポートの書き方
- 「図書館情報技術論」レポートの参考例
- 「図書館制度・経営論」レポートの書き方
- 「図書館制度・経営論」レポートの参考例
- 「図書館サービス概論」レポートの書き方
- 「図書館サービス概論」レポートの参考例
- 「情報サービス論」レポートの書き方
- 「情報サービス論」レポートの参考例
- 「児童サービス論」レポートの書き方
- 「児童サービス論」レポートの参考例
- 「図書館情報資源概論」レポートの書き方
- 「図書館情報資源概論」レポートの参考例
- 「情報資源組織論」レポートの書き方
- 「情報資源組織論」レポートの参考例
- 「図書館サービス特論」レポートの書き方
- 「図書館サービス特論」レポートの参考例
科目終末試験の対策
レポートを提出したら、いよいよ科目終末試験を受験することができます。
科目終末試験の設題や解答例は以下のページに載せているので、試験対策に役立ててください。