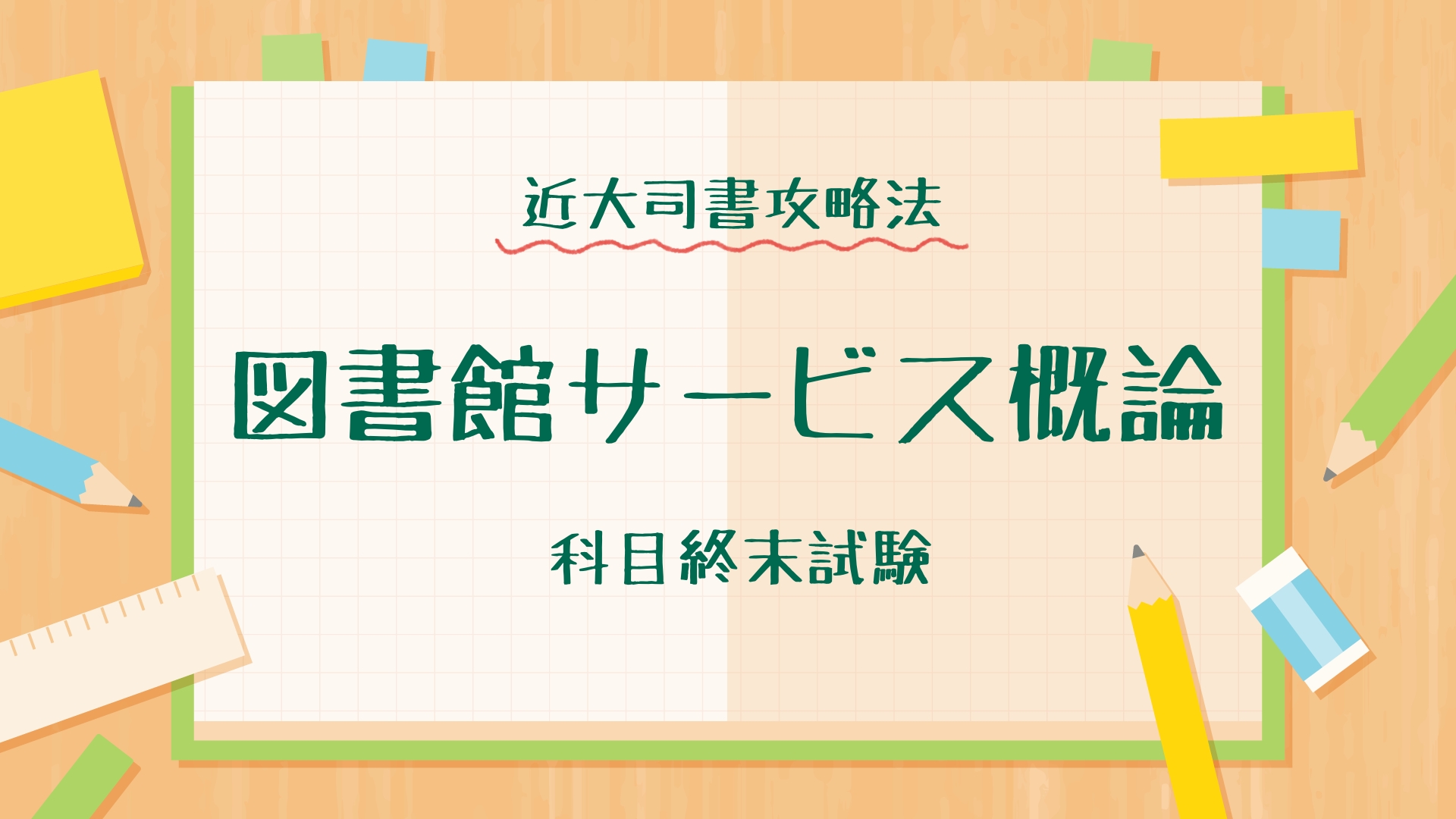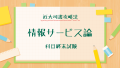このページでは、2023~2024年度版「図書館サービス概論」科目終末試験の解答例を掲載しています。
丸写しすると不合格になるため、あくまでも参考程度にとどめておいてください。
レポートの書き方や合格例については、こちらのページをどうぞ!
試験問題
レファレンスサービスについて、留意点とともに説明し、今後の課題を列挙してください。
解答例
序論
本論では、レファレンスサービスの概要及び留意点、現在の状況を踏まえた今後の課題について論じる。
レファレンスサービスの概要及び留意点
レファレンスサービスとは、利用者が何かを知りたいと思ったときに、図書館が調べものの支援をし、疑問を解決するパブリックサービスのことである。
レファレンスサービスには、直接的なレファレンスサービスと間接的なレファレンスサービスの2種類が存在する。
直接的なレファレンスサービスとは、図書館員が利用者と直接向き合い、実際にコミュニケーションを取りながら支援するサービスである。
一方、間接的なレファレンスサービスとは、利用者と直接対面でやり取りをする訳ではなく、利用者が自分で調べられるようにレファレンス資料を整備しておくなどして支援するサービスである。
また、利用者のレファレンス質問に対して館内の所蔵資料やデータベースのみで対応できない場合は、レフェラルサービスと呼ばれる、外部の機関に図書館員が照会して回答を得たり、利用者にその機関を案内したりするサービスもある。
さらに、これらのレファレンスサービスが参考図書などの既存の典拠に基づいて回答がなされるのに対し、新しく情報が確認できたときに情報を提供するカレントアウェアネスサービスも存在する。
今後の課題
近年のレファレンスサービスは、情報技術の発展によって、以前よりも利便性が高まっていると言える。
しかしながら、課題点もいくつか存在する。
1つ目は、レファレンスサービスの認知度、利用率の低さである。
図書館でできることは、読書や資料の貸出だけでなく、映画上映や教養講座などの行事に参加したり、インターネットを利用して調べものをしたりと多岐に渡るが、一方でレファレンスサービスの存在を知らない図書館利用者も少なくない。
そのため、図書館で調べものをしたいがどうしたらよいのか分からない、自力では解決が難しい、といった場合に、利用者がレファレンスサービスを頼れるよう掲示物や案内などで周知する必要がある。
また、具体的な対策として、レファレンスカウンターの設置場所や職員の配置を改善することが考えられる。
実際に、利用者は図書館員が何か作業をしているときに話しかけることを遠慮してしまうケースがあるため、貸出カウンターとレファレンスカウンターを切り離して設置することが効果的だと考えられる。
しかし、現状では、特に市区町村レベルの公共図書館において、貸出カウンターとレファレンスカウンターを一体で設置しているケースが多い。
貸出の利用者が並んでしまった場合などはレファレンスサービスの利用者が話しかけることを躊躇ってしまったり、あるいはレファレンスサービス担当の図書館員が貸出の応援に回らなければならなくなってしまったりと、レファレンスカウンターとしての機能が十分に発揮されないことが懸念される。
そのため、利用者の目に留まりやすい位置に貸出カウンターから切り離されたレファレンスカウンターを設置することで、利用者にレファレンスサービスの存在をアピールするとともに、利用を促進することが可能であると考えられる。
2つ目は、図書館員のレファレンススキルの向上である。
現在の図書館では司書資格を有していない自治体の正規職員が異動ローテーションの中で図書館に配属されるケースも多い。
そのため、レファレンスサービスに関して専門的知識を有していない図書館員がレファレンス業務にあたることもある。
その際、しっかりとレファレンスサービスを行う、もしくはしかるべき図書館員、機関に引き継げるよう、司書資格を有していない図書館員にも、研修などを通して積極的にレファレンス業務を学ぶ機会を提供することが重要である。
また、レファレンスサービスに関するマニュアルを整備することも効果的だと考えられる。
図書館員の特定の誰かに業務が偏るのではなく、全ての図書館員が必要最低限のサービスを提供できるよう、レファレンス協同データベースのように知見や事例を集積し、図書館員のレファレンススキル向上に役立てることが望ましい。
結論
本論では、公共図書館におけるレファレンスサービスの概要及び留意点、現在の状況を踏まえた今後の課題について論じてきた。
レファレンスサービスは司書の業務として欠かせないものであり、利用者がよりレファレンスサービスを身近に捉え、役立ててくれるよう、今後も環境の整備や図書館員のスキル向上に努めていくことが重要だと思う。
振り返り
今回の結果は88点(優)でした。
同時に受けた4科目の中で唯一の優だったので、あと2点で秀だったのに…と軽く落ち込みました。
今後の課題を2点書いたことで、それぞれの話が浅くなってしまった感があるので、1点に絞って書けばよかったかなと思います。
1発目の試験だったこともあり、テキストの該当箇所を探して内容をまとめるまでに思いの外時間がかかってしまったので、事前にそれぞれのキーワードの該当箇所を抜き出しておくことをオススメします。
レポートの書き方と参考例
科目終末試験を受けるには、事前にレポートを提出している必要があります。
レポートの書き方と参考例は、以下を参考にしてください。
また、他の科目については以下のページにそれぞれ掲載しています。
- 「生涯学習概論」レポートの書き方
- 「生涯学習概論」レポートの参考例
- 「図書館概論」レポートの書き方
- 「図書館概論」レポートの参考例
- 「図書館情報技術論」レポートの書き方
- 「図書館情報技術論」レポートの参考例
- 「図書館制度・経営論」レポートの書き方
- 「図書館制度・経営論」レポートの参考例
- 「情報サービス論」レポートの書き方
- 「情報サービス論」レポートの参考例
- 「児童サービス論」レポートの書き方
- 「児童サービス論」レポートの参考例
- 「図書館情報資源概論」レポートの書き方
- 「図書館情報資源概論」レポートの参考例
- 「情報資源組織論」レポートの書き方
- 「情報資源組織論」レポートの参考例
- 「図書・図書館史」レポートの書き方
- 「図書・図書館史」レポートの参考例
- 「図書館サービス特論」レポートの書き方
- 「図書館サービス特論」レポートの参考例
科目終末試験の対策
他の科目の科目終末試験の設題や解答例は以下のページに載せているので、試験対策に役立ててください。