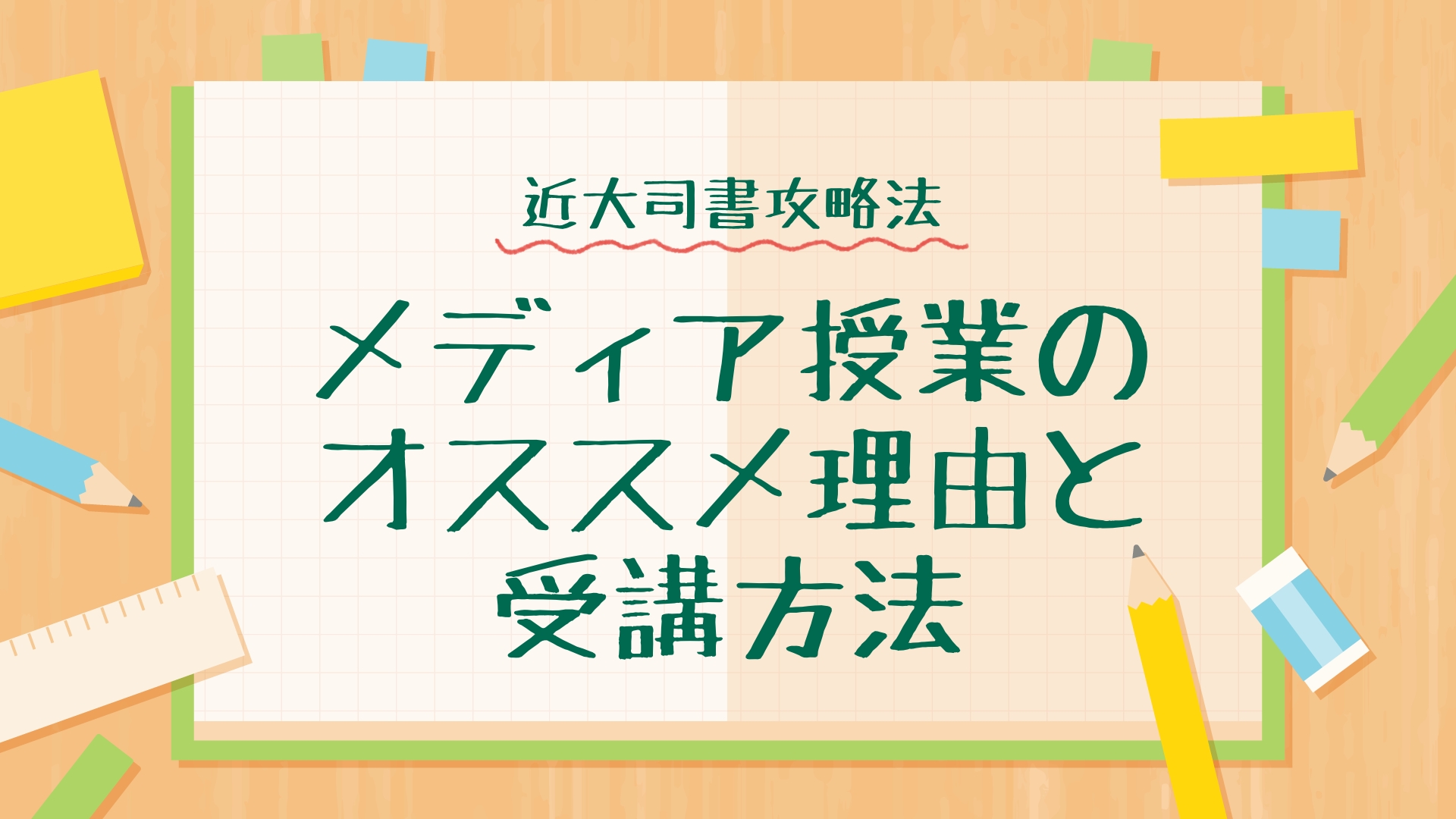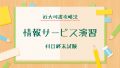近畿大学の司書課程のうち、面接授業科目である「情報サービス演習」と「情報資源組織演習」はメディア授業またはスクーリングでの受講が必須です。
ここでは、メディア授業をオススメする理由と、効率的な受講方法について説明します。
メディア授業をオススメする理由
メディア授業の最大のメリットは、いつでもどこでも受講が可能という点です。
スクーリングは近畿以外でも開講されていますが、あらかじめ定められた3~4日間の全日程に出席しなければならないため、仕事や家事育児と両立する人には少々厳しいかもしれません。
また、事前にスクーリング用のレポート課題があったり、グループワークがあったりすることを考えると、なるべくならメディア授業を受講した方が負担は軽いと思います。
あと、私は個人的に集団授業や人と一緒に勉強することが苦手なため、自分のペースで学習を進めたい方にもメディア授業がオススメです。
逆に、通信授業が孤独だという方や、リアルタイムで先生に質問したいという方には、スクーリングが向いているかもしれません。
中には「メディア授業は難しい」という声もあるので、自分のライフスタイルや学習計画に合わせてお好みで選んでください。
メディア授業の注意点
メディア授業は前期1回と後期1回しか受けられず、申込には早い段階での「情報サービス論」と「情報資源組織論」のレポート提出が必要になるので、注意してください。
なお、前期のメディア授業申込は4月初旬~中旬、後期の申込は10月初旬~中旬なので、それまでにレポートを提出しなければいけません。
受講申込が間に合わなければ、次の学期のメディア授業まで待つか、スクーリングを受講する必要があります。
(スクーリングの場合は、それぞれの回の申込期日に間に合えば受講可能です。)
入学して最初のメディア授業を逃すと、残り1回で確実に合格しなければならなくなってしまうので、できるだけ前半で受講することをオススメします。
「情報サービス論」と「情報資源組織論」のレポートについては、以下を参考にしてください。
メディア授業の選び方
メディア授業では、2名の先生からクラスを選べます。
個人の相性もあるため、どちらの先生がオススメかは一概には言えませんが、私は「情報サービス論演習」も「情報資源組織演習」もK先生を選択しました。
理由としては、以下の4つが挙げられます。
- 先人達のブログや掲示板を見ると、K先生を選択している人の方が多かったから。
- 同じ先生で統一した方が全体像を把握しやすいかと思ったから。
- 「情報資源組織演習」の科目終末試験は、先生によって記述式か一問一答式かで分かれていると聞いたから。(※掲示板情報のため、本当かどうかは分かりません。)
- 後述する理由から、小テストの結果が成績に含まれない方がやりやすかったから。
近大司書はとにかく情報戦な部分があるので、口コミや事前情報がほとんどないよりかは、多少なりともある先生の方が安心かなとは思います。
先人達の体験談も参考にしながら、自分に合った先生を見つけてください。
メディア授業の受講方法
メディア授業は、受講期間内であれば何度でも動画を視聴することができます。
ただし、次の動画に進むためには、前の動画を最後まで視聴していることと、回ごとに設けられた小テストに合格していることが必要です。
そのため、私は最初に全部の動画を開放しておき、自分の好きなタイミングで見返せるようにしていました。
動画は1本あたり10~15分くらいで、長くても20分程度なので、移動中やスキマ時間にとりあえず流しておいて、まずは何となく大まかな内容を掴んでおきます。
そのままの速度だとやや遅く感じますが、予備校などの映像授業と違って倍速ボタンはついていないので、Chromeの拡張機能「Video Speed Controller」を使って1.5倍速くらいで聞いていました。
また、小テストは何度でも受けることができ、採点もその場で終わるので、1回目はサクッと合格だけしておいて、後日復習がてら解答を繰り返しました。
何度も受験するのを前提にしていたので、先の理由に挙げた「小テストの結果が成績に響くのは避けたかった」というのはこのためです。
そんなこんなでメディア授業開始一週間後には両科目とも受講が終わっていました。
が、試験までの期間が空きすぎるとほぼ内容を忘れると思ったので、本格的に勉強したのは試験前1週間くらいです。
科目終末試験の出題傾向は事前に調べていたため、演習を中心にザッと復習してから試験に臨みました。
科目終末試験の対策
K先生の場合、「情報サービス演習」の試験は他の科目と同じ記述式で、「情報資源組織論」の試験は一問一答式です。
基本的には授業内の演習と同じような内容が出題されるので、演習問題をきっちり押さえておけば試験も難なくクリアできると思います。
実際の設題や解答例は以下のページを参考にしてください。
※「情報資源組織演習」は正解が決まっているため、解答を伏せています。
試験の際、『レファレンスブックス:選びかた・使いかた』や『日本十進分類法』などの参考文献が手元にあった方がいいというアドバイスを見かけますが、私の場合に関しては特に必要ありませんでした。
テキストも購入していませんでしたが、授業の内容だけで問題なく解答できました。
「情報サービス演習」では、授業内の演習で出てきた参考図書をとにかくスクショなりメモなりで残しておくことと、レファレンス協同データベースで似たような事例を調べることで対応できるのではないかと思います。(レファレンス以外の設題に当たったため、結局使わずじまいでしたが…。)
「情報資源組織演習」は、国立国会図書館サーチ、NDC Navi、基本件名標目表トピックマップの3サイトを駆使して乗り切りました。
K先生の場合、基本的には授業で習ったことが出てくるので、参考文献集めに奔走するくらいなら、動画をもう一周見返した方が合格率は上がると思います。
メディア授業の動画は何度でも見返せるので、授業内の演習を繰り返して完璧にしておきましょう!