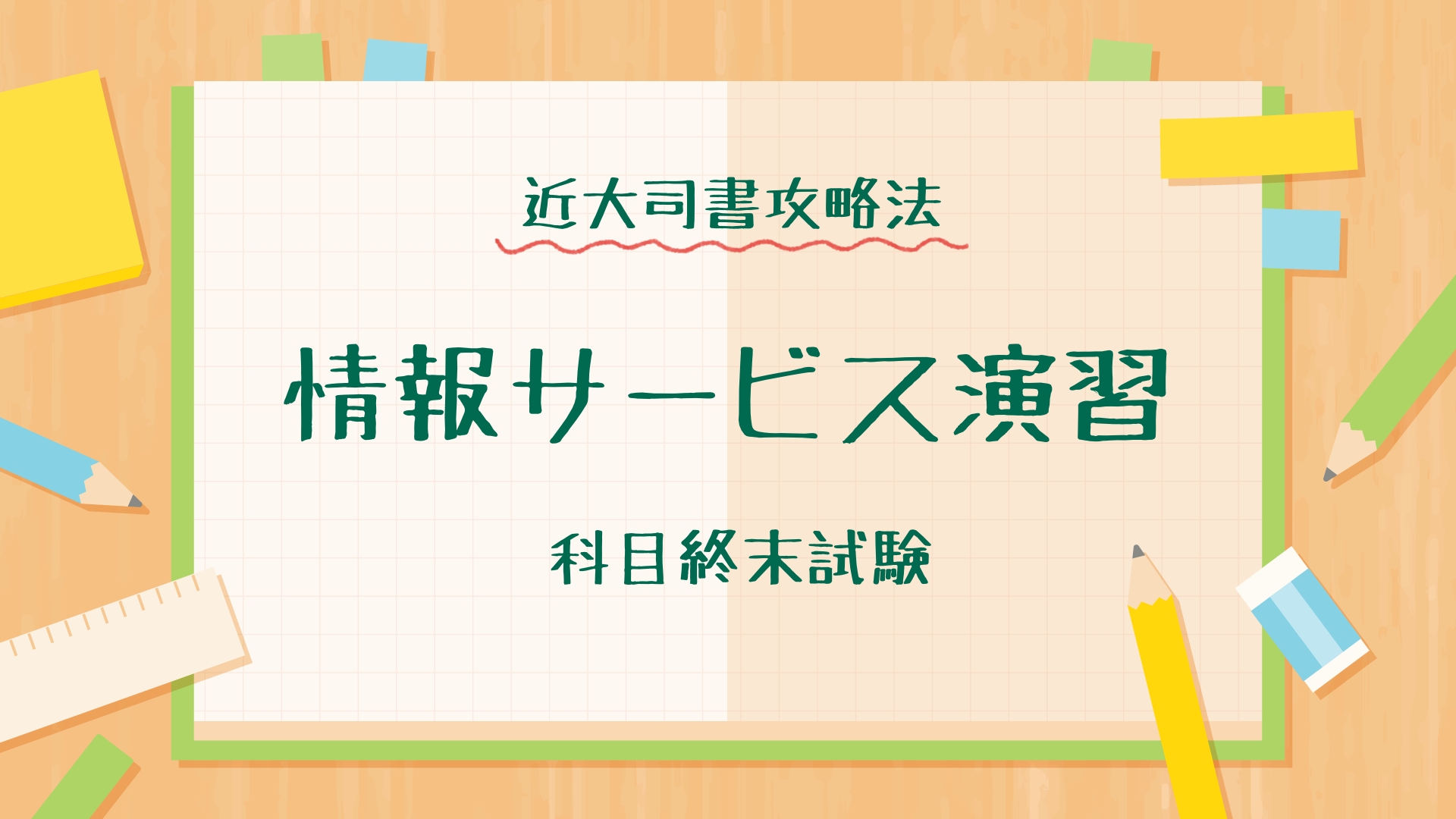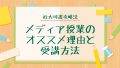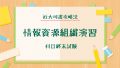このページでは、2023~2024年度版「情報サービス演習」科目終末試験(メディア授業)の解答例を掲載しています。
丸写しすると不合格になるため、あくまでも参考程度にとどめておいてください。
メディア授業の進め方や科目終末試験の対策については、こちらのページをどうぞ!
試験問題
参考図書を図書館内のどこに設置したら良いか、あなたの考えを述べなさい。
理由や想定される反対意見に対する反論も書くこと。
解答例
参考図書を設置する場所
私は、参考図書は一般図書とは別に、独立して配置されるべきであると考える。
また、調べものやレファレンスサービスの利便性を高めるため、可能な限りレファレンスカウンターの近くに配置し、図書館員の目が届くように工夫するべきであると思う。
私が以前利用したことがある公共図書館では、図鑑や事典などの参考図書が一般図書と混ざって配架されているケースがあった。
一方で、自分が住んでいる自治体の公共図書館や、自分の通っていた大学の大学図書館では、参考図書は一般図書とは分けて配架されており、調べものや論文を書く際に便利だったことを記憶している。
なお、近所の公共図書館では参考図書の棚は館内の奥まった場所に位置しており、あまり利用者もいない様子であったが、大学図書館ではレファレンスカウンターの近くに参考図書が配置されており、棚の前で資料を探すのに迷っていたり、何をどう調べたらよいか分からず質問したりしたときは、図書館員の方がすぐに出てきて、適切な参考図書を案内してくれた。
もちろん、公共図書館では一般図書を利用する利用者の方が多く、調べものをする利用者の方が少ないために、利用頻度に応じて配置を変えているという傾向があり、逆に大学図書館では参考図書の蔵書数が多く、重要性も高いために、分かりやすい場所に独立して配置されているという可能性が想定される。
しかしながら、実際に自分が調べものをしたり、レファレンスサービスを利用したりした経験から、私は参考図書が分かりやすく配置されていることと、適切なレファレンスサービスに繋げられるようにレファレンスカウンターの近くに参考図書が配置されていることが望ましいと考えている。
想定される反対意見とその反論
参考図書と一般図書を完全に分離して配置するという点については、次のような反対意見が想定される。
例えば、図書館の使い方や調べものに慣れていない利用者にとっては、一般図書と同じように配置されている方が資料が探しやすいのではないか、という意見である。
しかしながら、貸出を中心とする一般図書とは違い、参考図書には禁帯出のものも少なくない。
貸出可能な一般図書と混合して配置してしまうと、誤って禁帯出の資料を館外に持ち出してしまったり、本来の配架場所とは異なる場所に戻されてしまったり、貴重な資料であれば盗難の恐れもある。
図書館の使い方に慣れていない利用者だからこそ、一般図書とは区別して配置した方が、その資料が参考図書であることが分かりやすいのではないかと私は考える。
また一方で、調べものに慣れている人にとっては参考図書がまとまって配置されている方が資料を探しやすいことも考えられるだろう。
参考図書は図書館員もレファレンスサービスで使用することが多いため、急な依頼でも即時に対応できるよう、レファレンスカウンターや貸出カウンターの近くに参考図書がまとまって配置されていることが望ましいのではないだろうか。
また、参考図書の数があまり多くない、分室などの小規模な図書館の場合、参考図書を独立して配置する物理的スペースがない可能性も想定される。
先述の参考図書と一般図書を混合して配置している公共図書館の場合は、駅に併設されているタイプの町立図書館だったため、物理的な制約と蔵書数の観点から、参考図書と一般図書を分けずに配架しているという事情も考えられる。
しかしながら、その図書館内では、参考図書が一般図書に混ざって配架されている一方で、地域資料や郷土資料は特設コーナーを設けられていた。
駅に併設している地方の図書館という地域柄もあるとは思うが、棚の配置や資料種別の掲示など、配架スペースに制限がある図書館の場合でも、工夫の余地があるのではないかと考える。
図書館内の配置は、何よりもまず利便性と分かりやすさを優先して考えられるべきだと私は思う。
どの図書館においても、物理的や人員的に様々な制約があるのは変わりない。
そのため、限られたスペース、あるいは人員の中で、どのように利用者へ高品質なサービスを提供するかを考え、工夫し、改善していくのが図書館員の責務ではないかと私は考える。
振り返り
今回の結果は80点(優)でした。
てっきりレファレンスの演習問題が出るかと思い、レファレンス事例集などの用意をしていたのですが、予想と異なる設題が出てちょっとだけ拍子抜けしました。
メディア授業以外の科目と同様に、K先生の「情報サービス演習」は記述方式となります。
他の方の体験談を見るに、レファレンス関連の設題(「~に関する参考図書を●点挙げよ。」など)が出る場合もあるようなので、授業内で扱った内容は可能な限り網羅しておくことをオススメします。
レポートの書き方と参考例
メディア授業を受講するには、事前にレポートを提出している必要があります。
レポートの書き方と参考例は、以下を参考にしてください。
また、他の科目については以下のページにそれぞれ掲載しています。
- レポート作成の手順と注意点
- 「生涯学習概論」レポートの書き方
- 「生涯学習概論」レポートの参考例
- 「図書館概論」レポートの書き方
- 「図書館概論」レポートの参考例
- 「図書館情報技術論」レポートの書き方
- 「図書館情報技術論」レポートの参考例
- 「図書館制度・経営論」レポートの書き方
- 「図書館制度・経営論」レポートの参考例
- 「図書館サービス概論」レポートの書き方
- 「図書館サービス概論」レポートの参考例
- 「児童サービス論」レポートの書き方
- 「児童サービス論」レポートの参考例
- 「図書館情報資源概論」レポートの書き方
- 「図書館情報資源概論」レポートの参考例
- 「情報資源組織論」レポートの書き方
- 「情報資源組織論」レポートの参考例
- 「図書・図書館史」レポートの書き方
- 「図書・図書館史」レポートの参考例
- 「図書館サービス特論」レポートの書き方
- 「図書館サービス特論」レポートの参考例
科目終末試験の対策
メディア授業のもう一つの科目「情報資源組織演習」の設題については、以下のページで説明しています。
他の科目の科目終末試験の設題や解答例は以下のページに載せているので、試験対策に役立ててください。