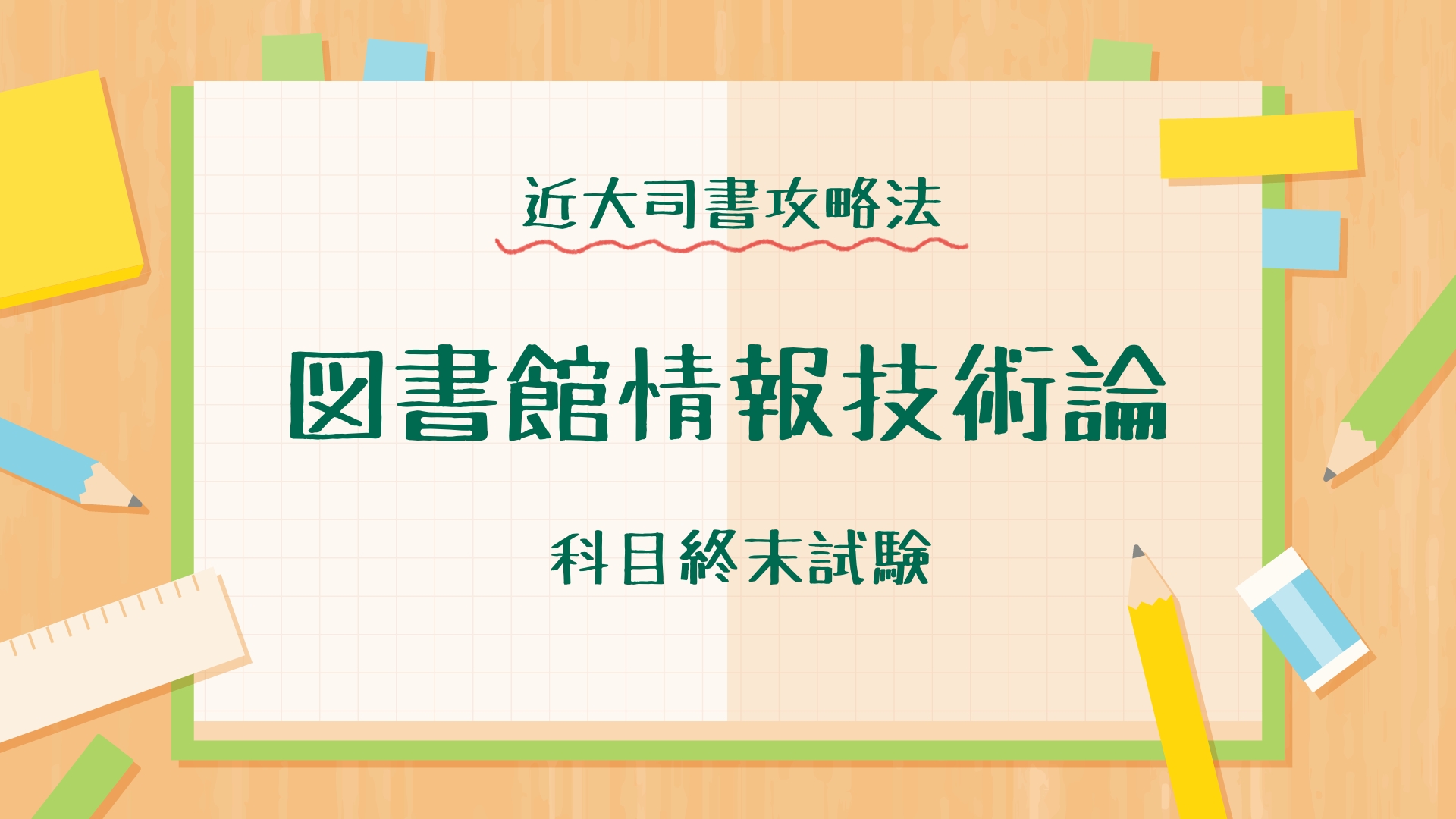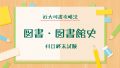このページでは、2023~2024年度版「図書館情報技術論」科目終末試験の解答例を掲載しています。
丸写しすると不合格になるため、あくまでも参考程度にとどめておいてください。
レポートの書き方や合格例については、こちらのページをどうぞ!
試験問題
図書館では現在かつ将来期待される技術として、(web)ディスカバリーサービスが、話題になっています。
(web)ディスカバリーサービスとはどういう機能のことですか?
わかりやすく説明してください。
また(web)ディスカバリーサービスにはどういう商品(ソフトやシステム)が開発されているのか、具体的な事例も含めて紹介してください。
(1000文字程度)
解答例
(web)ディスカバリーサービスとは
(web)ディスカバリーサービスとは、紙の図書や雑誌、データベース、電子ジャーナルなどを同一の画面で検索できる統合検索機能のことを指す。
検索対象に図書館の内外は問わず、データベースや電子ジャーナルに掲載されている論文や記事など、特定の図書館に所蔵されていない学術資料も検索できる点において、蔵書検索が基本のオンライン閲覧目録(Online Public Access Catalog:OPAC)とは異なる性質を持つ。
従来では、書籍や学術文献(学術論文等)、新聞記事の検索にはそれぞれ特化したデータベースや検索システムを個別に用いる必要があったが、(web)ディスカバリーサービスではそれらをまとめて検索することができる。
一括検索や横断検索という意味ではポータルサイトとも似ているが、ポータルサイトが主にデジタルアーカイブなどのデジタルコンテンツを対象としており、同種の情報源や同じ機関からの各種の情報源などを提供するものであることに対して、(web)ディスカバリーサービスは所蔵されている紙の資料も対象に含む点、それぞれの(web)ディスカバリーサービスにおいて特定の分野や発信元に限らない多種多様な情報源を設定できる点で、ポータルサイトとも一線を画する。
また、GoogleやYahooなどの一般的な検索エンジンとは違い、データベースや電子ジャーナルなどの有料契約が必要な学術資料も検索対象に含まれるため、より学術的に高度な検索をすることが可能である。
蔵書検索だけではない、電子データに強い次世代型のOPACとして、大学図書館などでの導入が進んでいる。
(web)ディスカバリーサービスの事例
(web)ディスカバリーサービスには、各大学で独自に構築されているものや、「東京都立図書館ディスカバリーサービス」などの公共図書館で構築されているものなどがある。
また、「EBSCO Discovery Service」という、民間企業が提供する様々なデータベースの共通(web)ディスカバリーサービスも存在する。
これらのような民間企業の提供するサービスを導入している大学も存在する。
(910字)
振り返り
今回の結果は75点(良)でした。
図書館情報技術論はテキストに載っていない問題が出ると巷で噂の科目ですが、まさか本当に出るとは思いませんでした。
テキストに書いてある関連記述も多少取り入れつつ、試験時間のほとんどを調べることに費やしましたが、明確な模範解答がない中でも何とか合格できてよかったです。
レポートの書き方と参考例
科目終末試験を受けるには、事前にレポートを提出している必要があります。
レポートの書き方と参考例は、以下を参考にしてください。
また、他の科目については以下のページにそれぞれ掲載しています。
- 「生涯学習概論」レポートの書き方
- 「生涯学習概論」レポートの参考例
- 「図書館概論」レポートの書き方
- 「図書館概論」レポートの参考例
- 「図書館制度・経営論」レポートの書き方
- 「図書館制度・経営論」レポートの参考例
- 「図書館サービス概論」レポートの書き方
- 「図書館サービス概論」レポートの参考例
- 「情報サービス論」レポートの書き方
- 「情報サービス論」レポートの参考例
- 「児童サービス論」レポートの書き方
- 「児童サービス論」レポートの参考例
- 「図書館情報資源概論」レポートの書き方
- 「図書館情報資源概論」レポートの参考例
- 「情報資源組織論」レポートの書き方
- 「情報資源組織論」レポートの参考例
- 「図書・図書館史」レポートの書き方
- 「図書・図書館史」レポートの参考例
- 「図書館サービス特論」レポートの書き方
- 「図書館サービス特論」レポートの参考例
科目終末試験の対策
他の科目の科目終末試験の設題や解答例は以下のページに載せているので、試験対策に役立ててください。