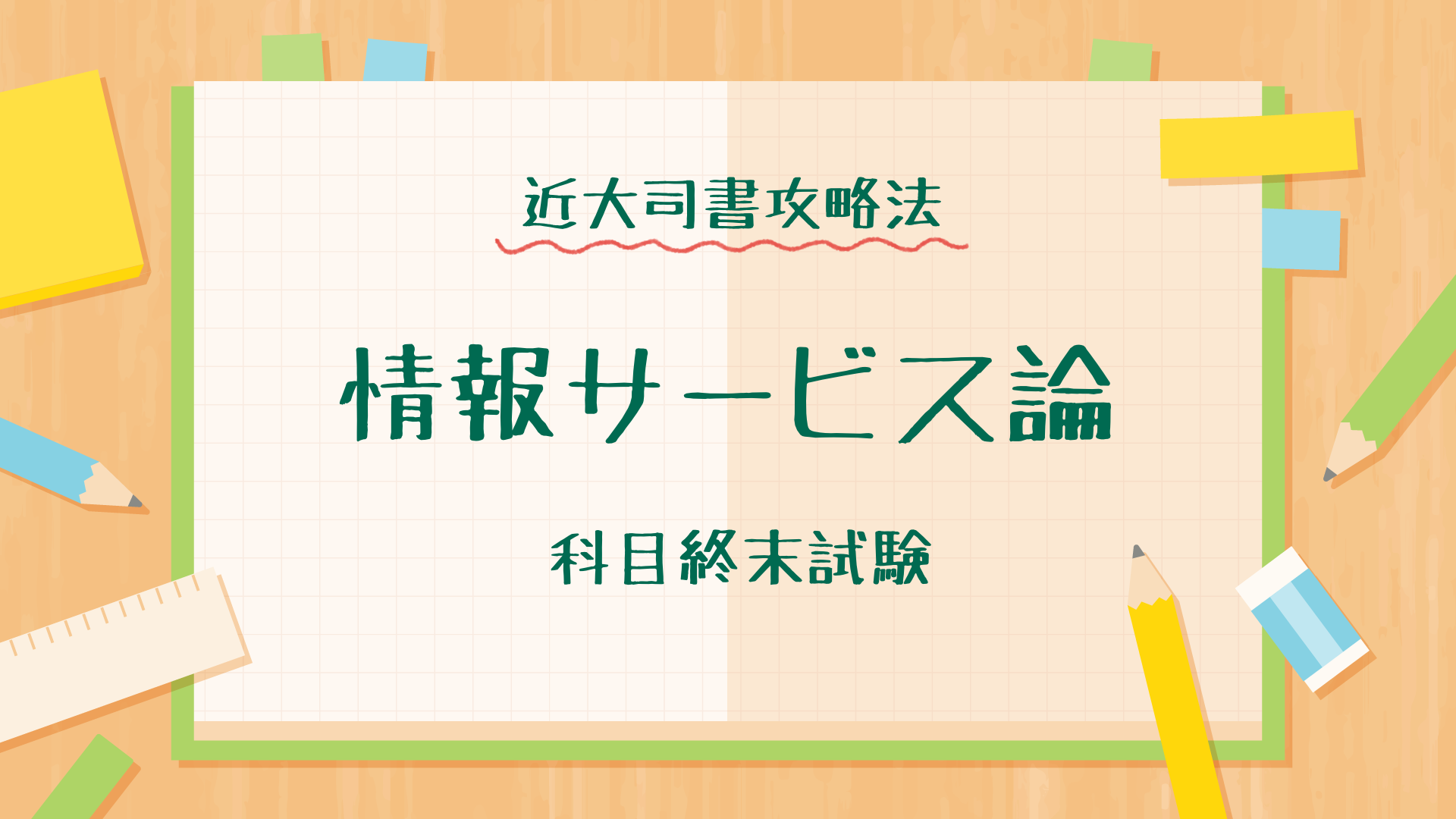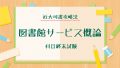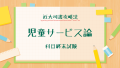このページでは、2023~2024年度版「情報サービス論」科目終末試験の解答例を掲載しています。
丸写しすると不合格になるため、あくまでも参考程度にとどめておいてください。
レポートの書き方や合格例については、こちらのページをどうぞ!
試験問題
「情報サービスの種類」における図書館の相互協力の種類を4点挙げ、それぞれについてその内容を述べた後、その内の「相互レファレンス」に着目し、相互レファレンスを充実させるには、どのような工夫が必要か、貴方自身の考え方を含め記して下さい。
解答例
序論
本論では、「情報サービスの種類」における図書館の相互協力の種類4点とその内容について述べた後、相互レファレンスを充実させるにはどのような工夫が必要か、自らの考えを論じる。
「情報サービスの種類」における図書館の相互協力の種類と内容
相互協力とは、公共図書館、学校図書館、大学図書館、専門図書館など、全ての図書館同士が協力しあって行うものである。
相互協力制度のサービスはレファレンス係が担当している。
相互協力には、以下の4種類が存在する。
図書の相互貸借
憲法の「知る権利」を保障するという視点や人類が構築してきた知的財産を保存・提供するという図書館の使命から、特別事情がない限り、全ての図書館が実施しなければならないものである。
具体的な例としては、国立国会図書館と公共・大学図書館との相互貸借、都道府県図書館と市町村図書館、大学図書館同士等々がある。
資料の相互文献複写
図書・雑誌等の図書館資料を他の図書館と相互にコピーサービスを行うものである。
ほとんどの図書館で行っているサービスで、自館に持っていない資料でも相互協力によって容易にコピー物を入手することができる。
特に、海外や遠方の図書館に対しては効果的である。
相互協力の大原則はギブ・アンド・テイクであり、決して一方的にならないような蔵書検索を行い、保存においても相互協力の観点から特色を持たせる等、気配りが必要である。
相互利用紹介
他の図書館を紹介するものであり、主として近郊にある図書館同士で行われる。
紹介状の発行等によって、大学図書館同士、大学図書館と専門図書館、公共図書館と大学図書館など、館種を超えて行われる。
特定地域の図書館では、公共・大学・私立図書館が一体となって共通閲覧券を発行しているところもある。
質問処理の相互レファレンス
レファレンス質問に対して、自館で解決できない場合、他の図書館のレファレンス係の協力を得たり、他の図書館の主題司書(サブジェクトライブラリアン)を紹介するなどして解決するものである。
レファレンス質問は多岐にわたり、全分野といっていいほど多様であるため、他の図書館にいるレファレンス係との人的ネットワークが不可欠である。
相互レファレンスを充実させるための工夫
先述したとおり、多様なレファレンス質問に対応するためには、各図書館のレファレンス係との人的ネットワークが不可欠である。
したがって、このような人的ネットワークを形成するために、地域、館種の垣根を超えたレファレンス研修会の充実を図ることが必要ではないかと私は考える。
人的ネットワークを作る努力をすることは、レファレンス係の大事な仕事である。
各図書館にどのようなレファレンス係がいるのかを把握し、彼らと円滑な連携を取るためには、実際にレファレンス係同士が交流する機会を設けることが効果的であると考える。
また、レファレンス担当者が目標とすべきは主題司書(サブジェクトライブラリアン)である。
主題司書は、高度な情報を提供することが可能になるとともに、利用者の要求を的確に捉え、信頼度を高めることができ、資料の選定や参考図書の評価を適切に行うことができる。
欧米先進国では、司書は各自が何らかの専門主題を持ち、除籍力を育成し、豊かな知識を有している。
主題図書を育成するには主題別組織などの環境の整備が必要だが、日本では主題別組織を採用している図書館は少なく、主題司書の育成ができにくい環境にあるため、個々人が主題司書になるべく努力すること、加えて司書が努力するための環境を整備することが大切だと考える。
研修会などを通して各図書館の司書が集まり、意識を高め、知見を深める場が増えれば、その館のみならず、全体的な司書のレファレンス能力及び意識の向上が期待できる。
さらに、どの図書館にどのような主題について強みを持つ司書がいるのかを把握すれば、効率的で質の高い情報サービスを提供することに繋がると考えられる。
結論
本論では、情報サービスの種類における図書館の相互協力の種類と内容、相互レファレンスを充実させるための工夫について論じてきた。
相互協力の根底にあるのはギブ・アンド・テイクの精神であり、それぞれの司書がそのような意識を持って協力していくことが欠かせない。
資料だけではなく、人同士の人的ネットワークも必要であるため、日々コミュニケーションや交流のスキルを磨いていく必要があると考える。
振り返り
今回の結果は90点(秀)でした。
前半の説明部分で思いの外時間を取られたため、後半は駆け足になってしまいましたが、何とか秀を取れてよかったです。
レポートの書き方と参考例
科目終末試験を受けるには、事前にレポートを提出している必要があります。
レポートの書き方と参考例は、以下を参考にしてください。
また、他の科目については以下のページにそれぞれ掲載しています。
- 「生涯学習概論」レポートの書き方
- 「生涯学習概論」レポートの参考例
- 「図書館概論」レポートの書き方
- 「図書館概論」レポートの参考例
- 「図書館情報技術論」レポートの書き方
- 「図書館情報技術論」レポートの参考例
- 「図書館制度・経営論」レポートの書き方
- 「図書館制度・経営論」レポートの参考例
- 「図書館サービス概論」レポートの書き方
- 「図書館サービス概論」レポートの参考例
- 「児童サービス論」レポートの書き方
- 「児童サービス論」レポートの参考例
- 「図書館情報資源概論」レポートの書き方
- 「図書館情報資源概論」レポートの参考例
- 「情報資源組織論」レポートの書き方
- 「情報資源組織論」レポートの参考例
- 「図書・図書館史」レポートの書き方
- 「図書・図書館史」レポートの参考例
- 「図書館サービス特論」レポートの書き方
- 「図書館サービス特論」レポートの参考例
科目終末試験の対策
他の科目の科目終末試験の設題や解答例は以下のページに載せているので、試験対策に役立ててください。
- 科目終末試験の注意点と設題一覧
- 「図書館サービス概論」科目終末試験の解答例
- 「児童サービス論」科目終末試験の解答例
- 「情報資源組織論」科目終末試験の解答例
- 「図書・図書館史」科目終末試験の解答例
- 「図書館情報技術論」科目終末試験の解答例
- 「図書館情報資源概論」科目終末試験の解答例
メディア授業の科目終末試験
「情報サービス論」のレポートを提出すると、面接授業科目の「情報サービス演習」を受講できるようになります。
メディア授業を選択した場合の受講方法と科目終末試験の対策については、以下のページで説明しています。