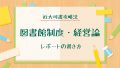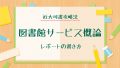このページでは、2023〜2024年度版「図書館制度・経営論」レポートの合格例を掲載しています。
丸写しすると再提出になるため、自分の言葉に置き換えるなど適宜アレンジしてください。
書き方のコツは、こちらのページで説明しています。
レポート全体の注意点や順番については、こちらのページを参考にしてください。
レポート設題
「図書館経営の基本思考」における「未来思考」の5点について簡潔明瞭に説明した後、その「未来思考」を受けて、今後の専門職としての司書のあるべき姿を論じるとともに、それに伴う図書館運営のあり方を、貴方自身の考え方を含め論じて下さい。
解答例
序論
本論では、図書館経営における「未来思考」の概要を説明し、今後の専門職としての司書のあるべき姿と図書館運営のあり方について論じる。
本論
「未来思考」について
「未来思考」とは、激動の時代を生きる図書館が今後どのように未来を予測し、それに適応した経営を行っていくか、巷に溢れるさまざまな情報をどのようにして今後の図書館経営に活かしていくかを検討するための土台となる考え方である。
この「未来思考」に必要な情報には、以下の5つが挙げられる。
文教政策情報
国や地方自治体等の教育行政に関する情報のことを指す。
近年は図書館においてもデジタルアーカイブなどのデジタル化が進んでいるため、経営の根本に関わる図書館法だけでなく、著作権法の改正など、さまざまな法規の制定改廃に注意を向ける必要がある。
社会変化情報
社会変化には、情報環境の変化、高齢化、高度学歴化、少子化など、さまざまなものが考えられる。
そのような社会変化は図書館の利用者にも変化を及ぼす。
そのため、社会変化に合わせて図書館も柔軟にサービス等を展開していく必要がある。
図書館界の変化情報
図書館のネットワークには、自治体等の親機関のほか、日本図書館協会等の図書館同士が繋がり合う連合団体も存在する。
親機関の方針は図書館の経営に大きく影響を及ぼし、連合団体での決定事項も考慮する必要がある。
そのような縦や横の繋がりを持つ図書館にとって、関係団体の動向に注目することは不可欠だと言える。
出版界・情報産業界の変化情報
先述のとおり図書館では近年デジタル化が進んでおり、資料形態においても、従来の紙資料だけではなく電子書籍などの電子資料が加わるなど、大きな変化が生じている。
このような出版形態の変化は図書館の予算編成や整備、備品調達の計画などの方策にも影響するため、出版界の動向は今後の政策を決定する上での重要な鍵となる。
また、図書館は「知る権利」を保障する唯一の公的機関であるため、インターネット等の情報産業界の動向にも目を向ける必要がある。
マーケティング変化情報
図書館経営には、利用者が図書館に何を求めているのか、そのニーズを把握し、反映させていくという利用者中心思考が欠かせない。
近年ではインターネットの普及もあり、利用者のニーズもより多岐に渡っているため、調査等を通じてマーケティングの変化を意識していく必要がある。
今後の専門職としての司書のあるべき姿
現在、図書館における専門職とは司書資格を有している者のことを指し、文部科学省では司書の主な職務内容として、資料の選択や目録の作成、資料の貸出及び返却、レファレンスサービス、読書活動推進のための主催事業の企画立案や実施、自動車文庫などの館外奉仕活動の実施等が想定されている。
しかしながら、今後の専門職としての司書は、それだけでなく、情報を扱うスペシャリストとしての情報処理能力、デジタルスキルも必要になっていくと考えられる。
近年、デジタル化が進む図書館において、司書に求められる業務の幅はより広がりを見せている。
先に挙げた「未来思考」に必要な変化の情報にも、インターネットやデジタル機器の発展が変化の要因となっているケースが少なくない。
扱う媒体も紙資料だけでなく電子資料が増え、これからも更に既存のアナログサービスがデジタルサービスに移行していくことは想像に難くない。
そのようなデジタル化に際し、専門職たる司書はデジタルコンテンツを扱うパソコンスキルや情報リテラシー、著作権等に関する深い知識などを身につけ、知のインフラであるこれからの図書館を担っていく必要があると考える。
今後の図書館運営のあり方
現在、自治体では指定管理者制度を活用し、公民館などの業務を外部に委託する事例が増えている。
全国の指定管理者制度導入施設数は◯◯施設に上り、導入施設に占める図書館等の文教施設の割合は◯◯パーセントを占めている。
公務員の人員削減とともに、指定管理者制度を導入する自治体はこれからも増えていくことが予想される。
自治体直営の図書館は職員がジョブローテーションで配属されることが多く、必ずしも図書館業務に詳しくない者が携わる場合も少なくない。
そのため、指定管理者制度を導入して専門機関に運営を委託することは、専門職としての司書を担保することに繋がり、よりサービスの質向上にも寄与すると考えられる。
一方で、民間の指定管理者を導入する際には、情報セキュリティ面などでの注意点もある。
今後想定されうる人手不足の時代において、業務委託やAIなどを活用しながら、どのように業務を分担、効率化し、質の高いサービスを維持していくかが今後の図書館運営で重要になると考える。
参考文献
- 文部科学省「司書について」[https://www.mext.go.jp/a_menu/shougai/gakugei/shisyo/index.htm](アクセス日時:2024年8月31日)
- 総務省自治行政局行政経営支援室「公の施設の指定管理者制度の導入状況等に関する調査結果」2019年5月
書き方のコツ
書き方のコツは以下のページを参考にしてください。
また、他の科目については以下のページにそれぞれ掲載しています。
- 「生涯学習概論」レポートの書き方
- 「生涯学習概論」レポートの参考例
- 「図書館概論」レポートの書き方
- 「図書館概論」レポートの参考例
- 「図書館情報技術論」レポートの書き方
- 「図書館情報技術論」レポートの参考例
- 「図書館サービス概論」レポートの書き方
- 「図書館サービス概論」レポートの参考例
- 「情報サービス論」レポートの書き方
- 「情報サービス論」レポートの参考例
- 「児童サービス論」レポートの書き方
- 「児童サービス論」レポートの参考例
- 「図書館情報資源概論」レポートの書き方
- 「図書館情報資源概論」レポートの参考例
- 「情報資源組織論」レポートの書き方
- 「情報資源組織論」レポートの参考例
- 「図書・図書館史」レポートの書き方
- 「図書・図書館史」レポートの参考例
- 「図書館サービス特論」レポートの書き方
- 「図書館サービス特論」レポートの参考例
科目終末試験の対策
レポートを提出したら、いよいよ科目終末試験を受験することができます。
科目終末試験の設題や解答例は以下のページに載せているので、試験対策に役立ててください。