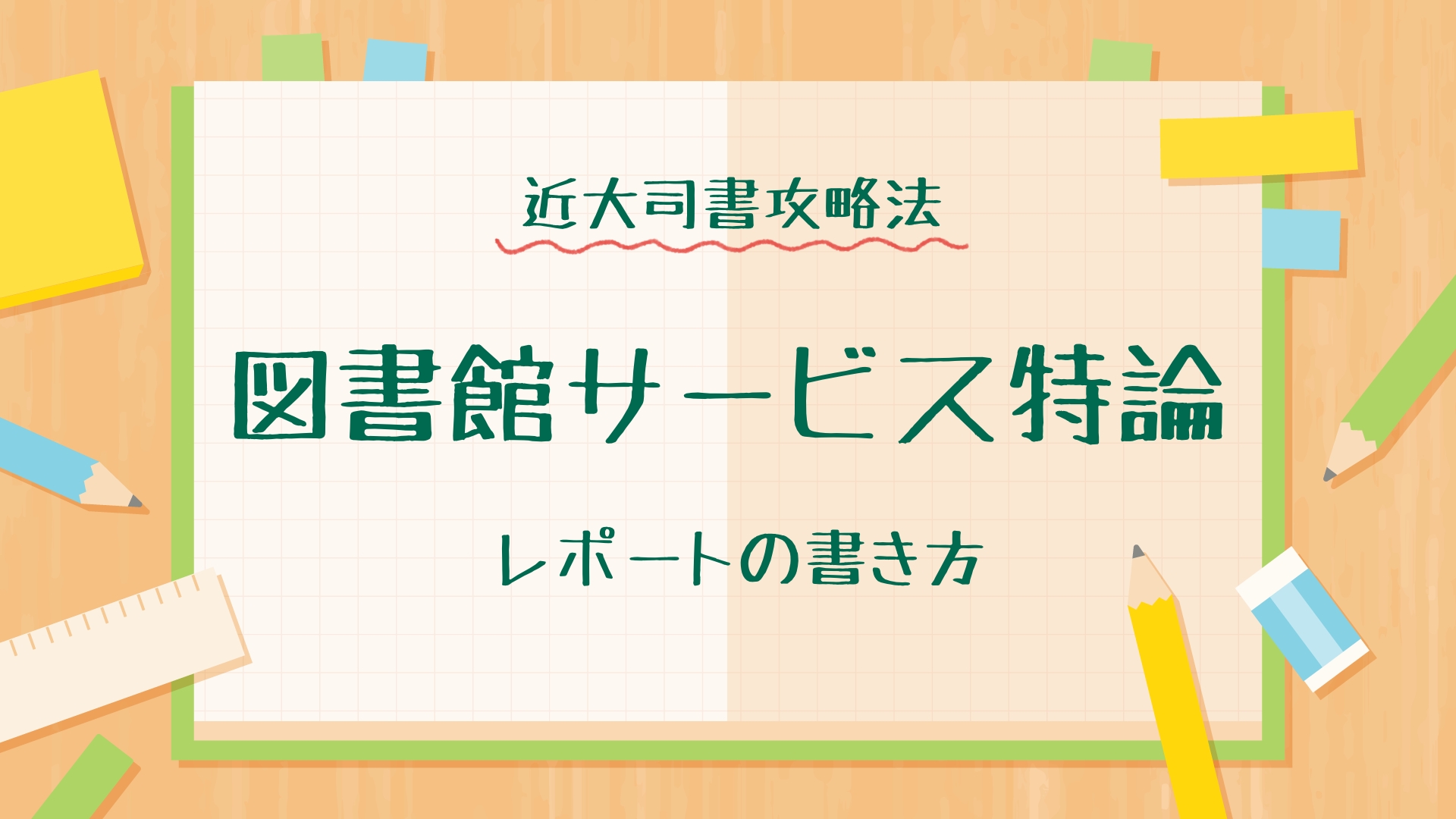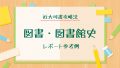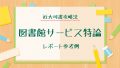このページでは、2023〜2024年度版「図書館サービス特論」レポートの書き方を説明しています。
ここで紹介しているやり方は必ずしも正しいとは限らず、あくまでも考え方の一つに過ぎません。
合格レポート例は、こちらのページを参考にしてください。
レポート全体の注意点や順番については、こちらのページで説明しています。
レポート設題
身近にある公共図書館を実際に観察し、その図書館で行われている課題解決支援サービスの内容及び特徴を述べると共に、設置されている地域の課題を考えると他にどのようなサービスが実現可能か具体的に提示しなさい。
評価のポイント
このレポートの評価基準は、実現可能な新しいサービスについて、いかにデータを揃えて根拠を明確にできるかです。
抽象的な言い方で恐縮ですが、とにかく根拠となる数値を並べまくるゴリ押し戦法しかないと思います。
講評を見た感じだと、ひとまず押さえるべきポイントは以下の3点です。
- 市民が抱える課題とは何か?
- 根拠とするデータは明確で理に適っているか?
- そのサービスは費用面、技術面で本当に実現可能なのか?
各ポイントについてどのようにクリアしていくかは後述します。
また、現在実施されている課題解決支援サービスは「図書館サービス概論」で書いた対象別サービスを使い回して、子育てや高齢化という地域の課題と絡めながら書くといい感じです。
書き方のコツ
市民が抱える課題を分析する!
ここで言う「課題」には、二つの意味があります。
一つ目は、その自治体や地域社会全体の課題です。
高齢化とか少子化とかそういう普遍的なやつですね。
二つ目は、図書館の利用者にとっての課題です。
例えば、図書館の開館時間が短くて仕事帰りに立ち寄れないだとか、立地が悪すぎて行けないとか、いわゆる利用者ニーズというやつです。
一つ目の地域の課題を考える際は、自治体の国勢調査結果などのデータを参考にして、その地域の人口がどうなっているかを調べます。
大体の地域では少子高齢化が進んでいると思うので、今回は高齢化を課題として考えていきます。
二つ目の利用者の課題は、図書館の利用者アンケートが参考になります。
高齢者向けのサービスを考える場合には、高齢者を対象とした世論調査も役立ちます。
それらの結果から、対象図書館に何が足りないのか、利用者は何を求めているのかを抜き出すとそれっぽくなります。
根拠データを揃える!
先で分析した二つの課題と、そこから導き出した課題解決支援サービスを支える根拠データを揃えます。
なお、自治体の政策や図書館の運営方針などから引用して「○○市の課題は○○だと言われている。したがって○○なサービスが必要…」的なことを書いただけだとあっさり再提出になるので注意してください。
他の科目とは異なり、「図書館サービス特論」において運営方針は根拠として扱われません。
根拠として有効なのは、数字や数値です。
他人や自治体の言葉を借りるのではなく、ここでは統計データをもとに自分で課題を見つけ出すことが求められます。
裏を返せば、「〇〇市では高齢化が進行している」とはっきり言えるだけのデータを揃えればいい訳です。
講評を見ると、次のようなデータが根拠として十分なようです。
- 過去20年分の人口の変化(増加しているか減少しているか)
- 過去20年分の高齢化率の変化
- 高齢化率の全国平均との比較(他の地域より高齢化が特に進んでいると言えるのか)
いずれも国勢調査からデータを引っ張ってこられるので、まずは自治体のホームページで国勢調査の結果を探しましょう。
過去20年分と書きましたが、国勢調査は5年ごとに行われているので、5年ごとのデータが3~4つあれば十分です。
全国平均との比較は、自治体が比較用に載せてくれているケースもありますが、載っていなかったら総務省のページなどから持ってきます。
サービスの実現可能性を考える!
根拠データをもとに課題解決支援サービスを考えたら、今度はそれが本当に実現可能かどうかを示さなければいけません。
「図書館概論」や「図書館サービス概論」ではその辺なぁなぁでも大丈夫だったのですが、課題解決支援サービスとして理に適っていても実現が難しいアイデアを書いてしまうと講評でつつかれます。
かといって、ありふれたサービスを書くとそれはそれで苦言を呈されるようなので、難しいところです。
実現可能であることを示すには、図書館の運営方針や基本計画に今後の実行プランとして書かれていないかが鍵になるでしょう。
あるいは、自治体の図書館協議会で似たようなサービスの話が出ていないか、その要望に対して自治体側がどのように回答しているかも参考になります。
図書館協議会の資料や議事録は自治体のホームページで公開されていると思うので、もし使えそうなものがあったら「このサービスについては図書館協議会でも検討がなされている」とか一言添えておくと説得力が増すと思います。
余談
正直、何で選択科目これにしちゃったかなぁ…ってくらい添削者が細かすぎて面倒臭い採点が厳しいので、可能であれば他の選択科目を選ぶことをオススメします。
近大司書に関しては、レポートの良し悪しは成績にあまり関係なく、あくまで科目終末試験を受けるための提出物のようなものなので、そこまで力を入れて書く必要もないと思います。
文句なしの完璧なレポートを作り上げるよりも、とにかく合格さえすれば講評で何を言われようがどうでもいいので、あまり気負わずさくっと要点だけをクリアしていきましょう。
レポートの参考例
実際のレポートは以下のページを参考にしてください。
また、他の科目については以下のページにそれぞれ掲載しています。
- 「生涯学習概論」レポートの書き方
- 「生涯学習概論」レポートの参考例
- 「図書館概論」レポートの書き方
- 「図書館概論」レポートの参考例
- 「図書館情報技術論」レポートの書き方
- 「図書館情報技術論」レポートの参考例
- 「図書館制度・経営論」レポートの書き方
- 「図書館制度・経営論」レポートの参考例
- 「図書館サービス概論」レポートの書き方
- 「図書館サービス概論」レポートの参考例
- 「情報サービス論」レポートの書き方
- 「情報サービス論」レポートの参考例
- 「児童サービス論」レポートの書き方
- 「児童サービス論」レポートの参考例
- 「図書館情報資源概論」レポートの書き方
- 「図書館情報資源概論」レポートの参考例
- 「情報資源組織論」レポートの書き方
- 「情報資源組織論」レポートの参考例
- 「図書・図書館史」レポートの書き方
- 「図書・図書館史」レポートの参考例
科目終末試験の対策
レポートを提出したら、いよいよ科目終末試験を受験することができます。
科目終末試験の設題や解答例は以下のページに載せているので、試験対策に役立ててください。