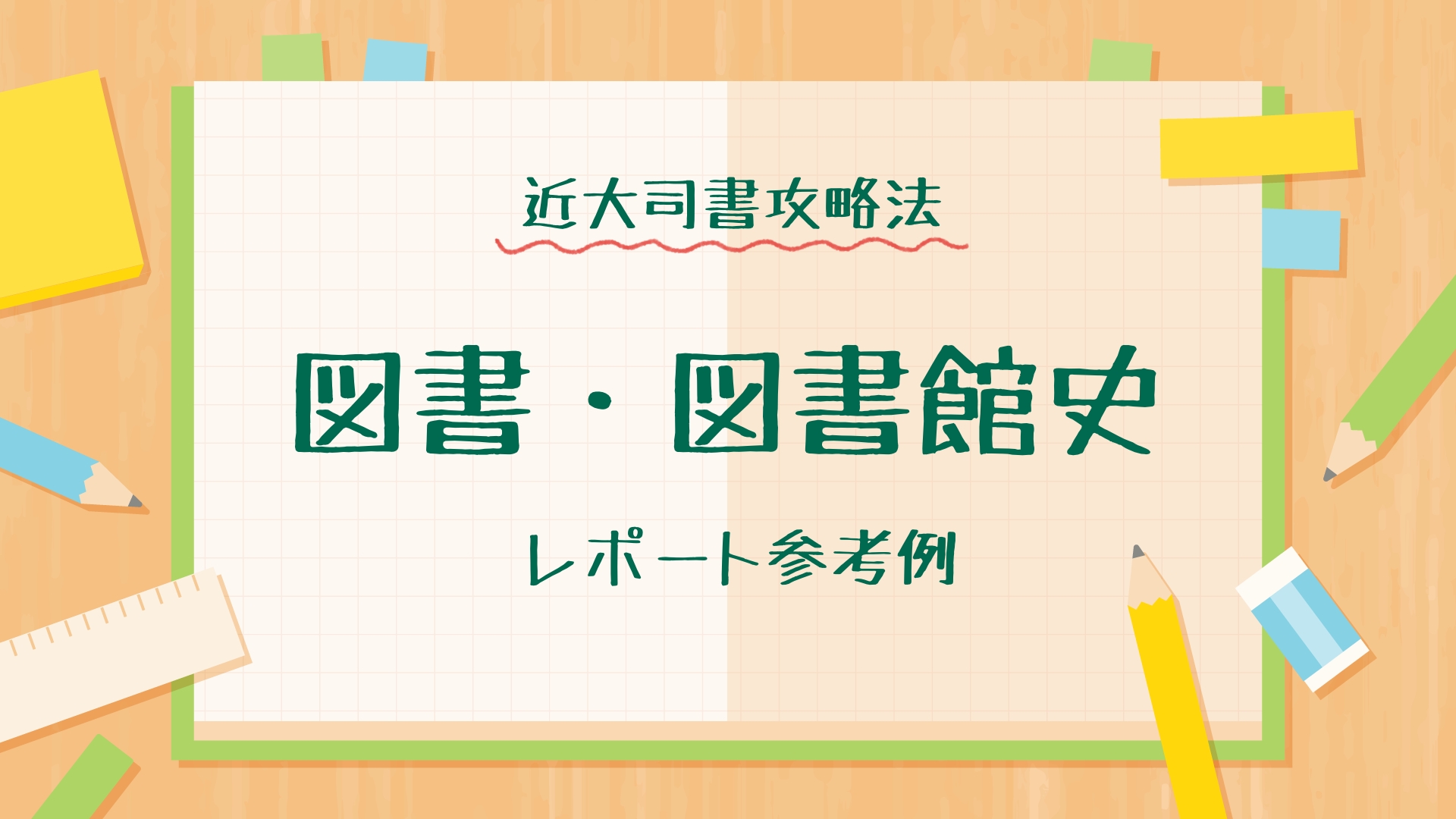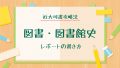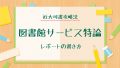このページでは、2023〜2024年度版「図書・図書館史」レポートの合格例を掲載しています。
丸写しすると再提出になるため、自分の言葉に置き換えるなど適宜アレンジしてください。
書き方のコツは、こちらのページで説明しています。
レポート全体の注意点や順番については、こちらのページを参考にしてください。
レポート設題
日本または西洋のどちらかを選び、それぞれの時代(古代、中世、近世、近代以降)の図書館発展の特徴をコンパクトに要約し、かつ私見(400字程度のまとめ)を述べてください。
解答例
古代
図書館は古代、中世、近世では王などの権力者が作るものだった。
権威の象徴だったからこそ、権力者が敗れたとき、文明が衰退したときには図書館も破壊された。
ニネヴェの王室図書館、アレクサンドリア図書館はまさしくその例であり、ウルピアを始めとするローマの図書館も、歴代のローマ皇帝が創設に関わっている。
ただし、ローマでは初めて一般市民に公開される公共図書館が出現し、図書館やそこに集積された知は王や学者らのものだけでなく、貴族から奴隷まで広く開かれるものとなった。
当初、本の素材は自然物をそのまま利用した木、粘土、石などであったが、メソポタミアの粘土版、エジプトのパピルスなどの自然物を原料とした加工品が用いられるようになり、次第に加工技術も発展し、より書きやすく丈夫な素材へと変化していった。
中世の羊皮紙(パーチメント)は作成に手間がかかり高価だったが、両面に書くことができ、冊子本にすることができるので収容文字量が大幅に増えた。
また、従来の巻子本と比べ冊子本は場所を取らないため、大量に所蔵が可能、持ち運びもしやすくなり、図書館から図書館へ本が移管されることも多くなった。
中世
中世の図書館は、キリスト教会や修道院に付随するもので、文化を継承する役割を果たしていた。
学術というよりも文化的、宗教的な色合いが強く、キリスト教というヨーロッパの軸と密接に結びついていたこともあり、戦いに巻き込まれて破壊されるなどの恐れを避けるためにも、大きな図書館が安定して存続するためにはキリスト教という権威を後ろ盾にする必要があったと推察される。
そのため、図書館の利用者は修道士などのキリスト教に携わる者が多かった。
この頃には大学が登場し、当時はまだ図書館を擁する大学はそれほど多くなかったものの、学術的な役割は以降大学図書館が担っていくこととなった。
中世の図書館は修道士が建てたものが多く、教義上の理由から、キリスト教関連の本が集められることがほとんどだったが、モンテ・カシーノ修道院図書館やヴィヴァリウム修道院図書館のように、宗教を問わず、ギリシャ・ローマの古典作品などあらゆる本を収集した図書館もあった。
また、修道院図書館には書写室が設けられており、写本の作製が多くなった。
この頃には羊皮紙本が主流になっており、冊子本であることから、装丁に技巧を凝らす例も見受けられた。
近世
近世になると、グーテンベルクの活版印刷術が発明されたことにより、職人が手で書き写していた写本から、インキュナブラを始めとする刊本の時代へと変化した。
これにより、大量の本が安価に生産できるようになった。
本が増加したことで貸出もしやすくなり、配架方法は箱や書見台から書架に変わり、図書館に併設される図書の生産施設は書写室から印刷所へと変わった。
中世の修道院図書館がキリスト教文化の継承の役割を担っていたことから、宗教戦争が起こると破壊され、修道院図書館に代わって市立図書館・教会図書館が出現した。
また、古代では知の集積所として機能し、身分や階級を問わず利用できていた図書館であったが、キリスト教と密接に関わっていたことで逆に利用者の層を狭めていた傾向が見られる。
近代
近代以降の図書館は、ヨーロッパとアメリカで発展の方向性が異なっていた。
ヨーロッパでは、図書館は未だ権威のためのものであり、フランス国立図書館や大英博物館図書館、ベルリン王立図書館など、元々は王などの権力者や特権階級の人物が建てた図書館がのちの国立図書館に発展するケースが見られたが、アメリカでは民衆によって民衆のための図書館が造られていた。
当初は大学図書館や会員制図書館、商業図書館、機械工図書館などの対象や分野を限定した社会図書館が多かったが、次第にピーターボーロ―公共図書館、ボストン公共図書館などの公共図書館が出現し、現代の図書館の在り方に近くなった。
現代では、本の電子メディア化が進んだこともあり、公共図書館は情報図書館としての機能を持ち、公共サービスとしてだけでなく、かつてのような知のインフラとしての役割も担っている。
私見
今となっては小説や雑誌など娯楽性も高い公共図書館だが、かつては学者が館長ならびに職員を務めており、所蔵された本の分野も学問性が高く、現在の大学図書館のような知のインフラとしての役割を果たしていたと見られる。
大学図書館の出現により知のインフラとしての役割は分離され、中世になってからは文化や宗教を象徴、伝承する役割へと変化した。
学術が盛んだった古代ギリシャ、キリスト教が栄えた中世ヨーロッパ、それらの時代の権威と結びついてきた図書館は、アメリカの自由主義の登場によって、権威ではなく、公共サービスとして広く提供されるものとなった。
時代とともに役割や蔵書の種類は移り変わっているが、その時代の最先端の知識、文化を提供する場としての図書館は、ずっと守られ続けていたのではないかと考える。
書き方のコツ
書き方のコツは以下のページを参考にしてください。
また、他の科目については以下のページにそれぞれ掲載しています。
- 「生涯学習概論」レポートの書き方
- 「生涯学習概論」レポートの参考例
- 「図書館概論」レポートの書き方
- 「図書館概論」レポートの参考例
- 「図書館情報技術論」レポートの書き方
- 「図書館情報技術論」レポートの参考例
- 「図書館制度・経営論」レポートの書き方
- 「図書館制度・経営論」レポートの参考例
- 「図書館サービス概論」レポートの書き方
- 「図書館サービス概論」レポートの参考例
- 「情報サービス論」レポートの書き方
- 「情報サービス論」レポートの参考例
- 「児童サービス論」レポートの書き方
- 「児童サービス論」レポートの参考例
- 「図書館情報資源概論」レポートの書き方
- 「図書館情報資源概論」レポートの参考例
- 「情報資源組織論」レポートの書き方
- 「情報資源組織論」レポートの参考例
- 「図書館サービス特論」レポートの書き方
- 「図書館サービス特論」レポートの参考例
科目終末試験の対策
レポートを提出したら、いよいよ科目終末試験を受験することができます。
科目終末試験の設題や解答例は以下のページに載せているので、試験対策に役立ててください。